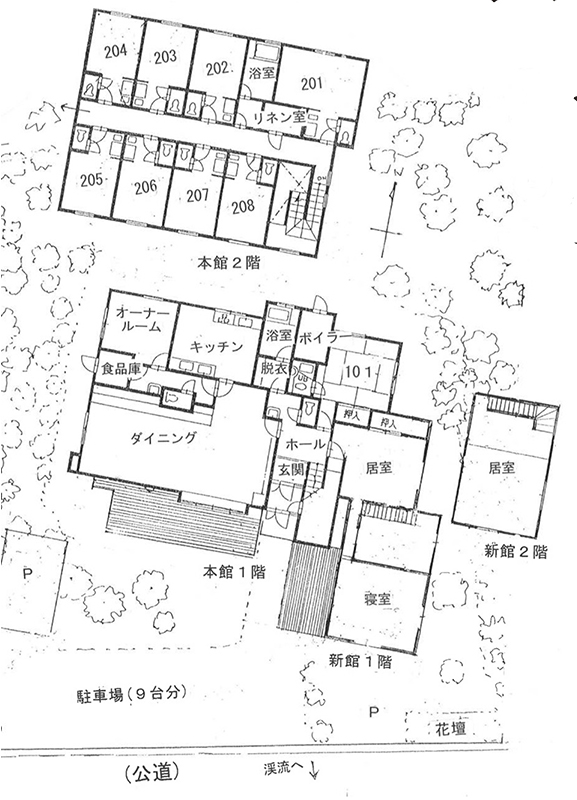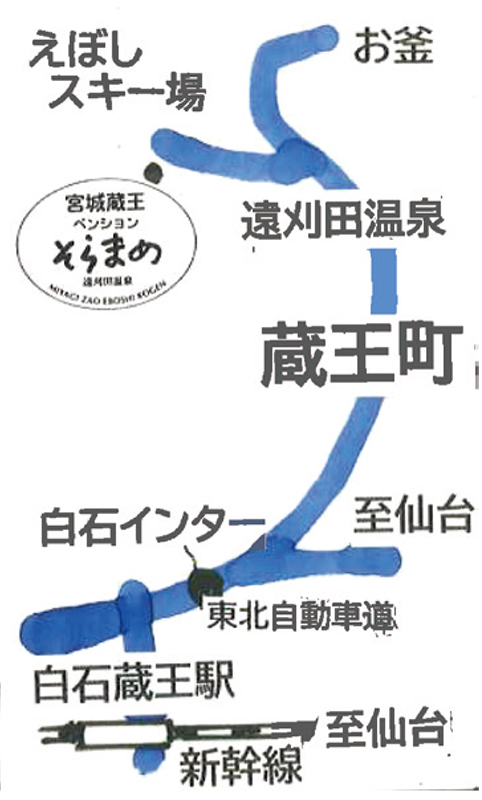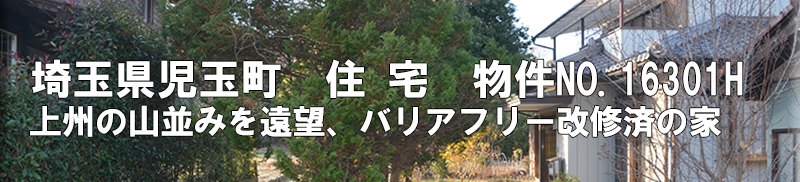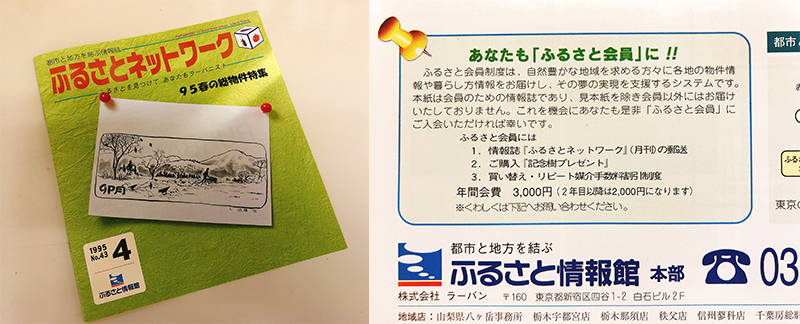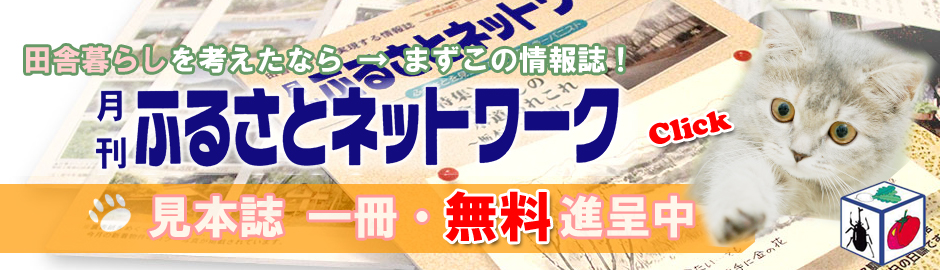▲骨寺村は中尊寺のかつての荘園がいまも残る場所。
▲骨寺村は中尊寺のかつての荘園がいまも残る場所。
吉里吉里国(きりきりこく)から人首(ひとかべ)へ
東北本線を走る車両が仙台を過ぎ、岩手との県境にさしかかると、突然東北弁が車内放送から流れ始めた。吉里吉里国が日本国から独立した瞬間だった。作家井上ひさしが描いた『吉里吉里人』(1981年刊)の冒頭だ。売れない三文作家の主人公・古橋と名前が同じだったわたしは、我がことのように井上の流れるような筆致と展開に引き込まれていったことを記憶している。
新幹線一ノ関駅あたりは北上川が作り出した肥沃な流域に広大な農地が広がり、それが途切れた西の山裾(やますそ)には平泉の世界遺産構成群が千年の都を静かに伝えている。十七世紀の終わりには松尾芭蕉も中尊寺を訪れ光堂の名句を残した。
東の山裾は桜の名所で西行法師が京に模すると絶賛した束稲山(たばしねやま)が横たわる。現代の「はやぶさ」は平均時速二百五十キロ以上の高速で移動していく。巻き上がる旋風によって吉里吉里人が話す流暢な東北弁はかき消され、それが入る余地はもはや無いようにもみえる。
地形的には奥羽山脈の東側では「くりこま高原」などの高山がそびえているため、それを乗り越えてくる雪は骨寺村や厳美渓ぐらいまでか。極端な標高差があるわけではないが、低山が広がる花巻市と比較するとこのあたりの降雪量は少なめだという。ことに今年の冬はまったくと言っていいほど雪はない。個人的には残念だ。
さて、遠野で用事を済ませたのち、もう一つの目的地である奥州市(おうしゅうし)江刺米里(えさしよねさと)へ向かった。関東在住の方が田舎暮らしをしたいと十数年前に都内の業者から購入した物件の売却相談があり、所有者の了解のもと今日はその物件の現況確認をする日だった。住所は特定できる。が、衛星写真では建物らしきものは写っていない。嫌な予感がした。
川に沿って県道水沢米里線を南下していくと右手に緑青色の山肌と、その手前には無人と思われる砕石工場が威容な姿をあらわしていた。さらに県道を進むと、川を過ぎたとたん急カーブが出現し、その両脇に歴史の重みを感じさせる町並みが突然姿をあらわした。旧街道筋に入ったのだ。
 ▲人首地区入口の急カーブ。
▲人首地区入口の急カーブ。
 ▲賢治が旅館から見たような町並みが残る。
▲賢治が旅館から見たような町並みが残る。
そこは「人首(ひとかべ)」と言われる地区でその名前に思わずたじろいでしまう。平安時代の「蝦夷(えにし)」伝説が息づく町と言われ、江戸期の伊達藩時代には街道の御番所もあった。明治期に入ると坂本龍馬のいとこが日本で初めてロシア正教の教えを駐在する役人に説いた。そしてビザンチン様式のハイカラな教会も建てられたという(しかし昭和8年の大火で焼失)。歴史的に見ても国内外の交流が盛んに行われてきた宿場町だ。
そして宮沢賢治もここを二度訪れている。最初は盛岡高等農林学校在学中の1917(大正6)年のことだ。地質調査で初めて江刺を訪問している。先ほどわたしも見た青い山肌もきっとご覧になり調査されたはずだ。
二度目は花巻で教壇に立っていた1924(同13)年。過酷な地質調査のため、自身の寿命があと15年だと知己にこぼしたあとのこと。この時は遠野側から峠越えをし、詩も創作している。一泊の旅。この日賢治の逗留した「菊慶旅館」は2011年に起きた東日本大震災で大打撃を受けてしまう。六つあった客室の天井の一部が崩落するなど建物は大きく損壊し、岩手県知事も宿泊したという名門旅館は廃業を余儀なくされてしまった。そして多くの方々に惜しまれつつ昨年秋に取り壊された。
 ▲街道筋に建つ趣のある洋風の家。
▲街道筋に建つ趣のある洋風の家。
人首で味わった高揚感を体のどこかに残しながらさらに南下。無人の小学校を過ぎ「チェーン着脱場」の標識にさしかかると、道路脇の雪がいちだんと増え始めた。目指す物件はもうすぐだ。
急な坂道を登っていくと数軒の集落があった。軒の深い民家がほどよく点在している。岩手の奥座敷に位置し農家民宿でもできそうな築百年を超えるほどのどっしりとした民家群だ。
携帯電話の衛星写真が指し示す物件の場所は雪に埋もれた道なき道の先だ。どうやら幅一メートルほどのこの道らしきところを行けば、売却相談を受けた物件にたどり着けるだろう。そう見当をつけて雪道での歩き方が下手なわたしは雪に足を取られながらゆっくりと一歩ずつ進む。百メートルほど行くと山から湧き出てきた水の流れがあった。そこが里と山の境のようだ。その境目に三軒の「家」が並んで建っていた。目指した物件はそのうちの一軒だった。
東北電力の古びた郵便物の住所地が所有者から教えられた所在地と一致したのだ。そこでわたしの見たものは、無残にも屋根が落ち、いたるところにカビが生えてしまった「家」であった。かつて人の住まいであったものがいわば「廃墟」と化していたのである。
時の過ぎ行くにまかせて人の手が入らずに朽ちつつあったのだ。放置され続けながらも風雪に耐えてきた「家」は、近い将来には確実に自然に帰す運命にあった。雪の中でたたずむ三軒は寄り添いながらその日を静かに待ち続けているようでもあった。
今回は、吉里吉里国も賢治の旅館も物件もいずれもタスキを引き継ぐことなく、わたしの中では残念ながら終わりを告げてしまった。こんなこともある。これが初めてでもないし最後でもないのだから。(北東北担当 中村 健二)
 ▲雪の中で育つタラノ木。
▲雪の中で育つタラノ木。
 ▲雪原を歩くキタキツネ。
▲雪原を歩くキタキツネ。 ▲鶴の写真を撮る人々。
▲鶴の写真を撮る人々。