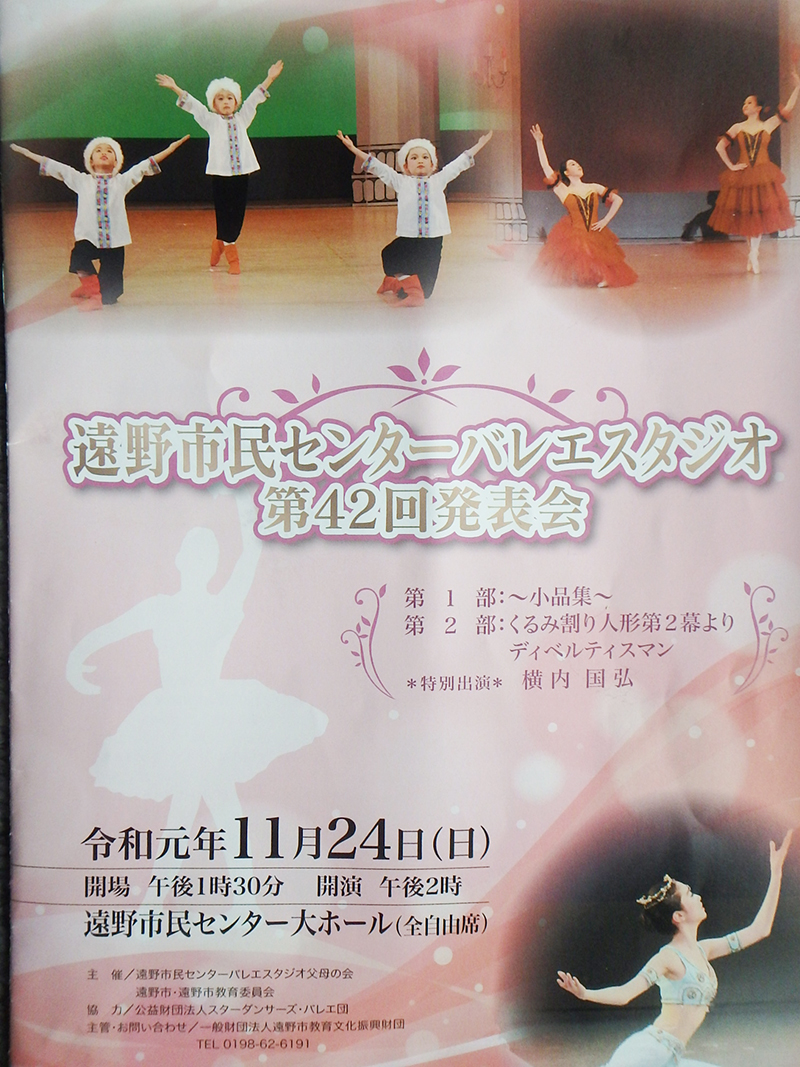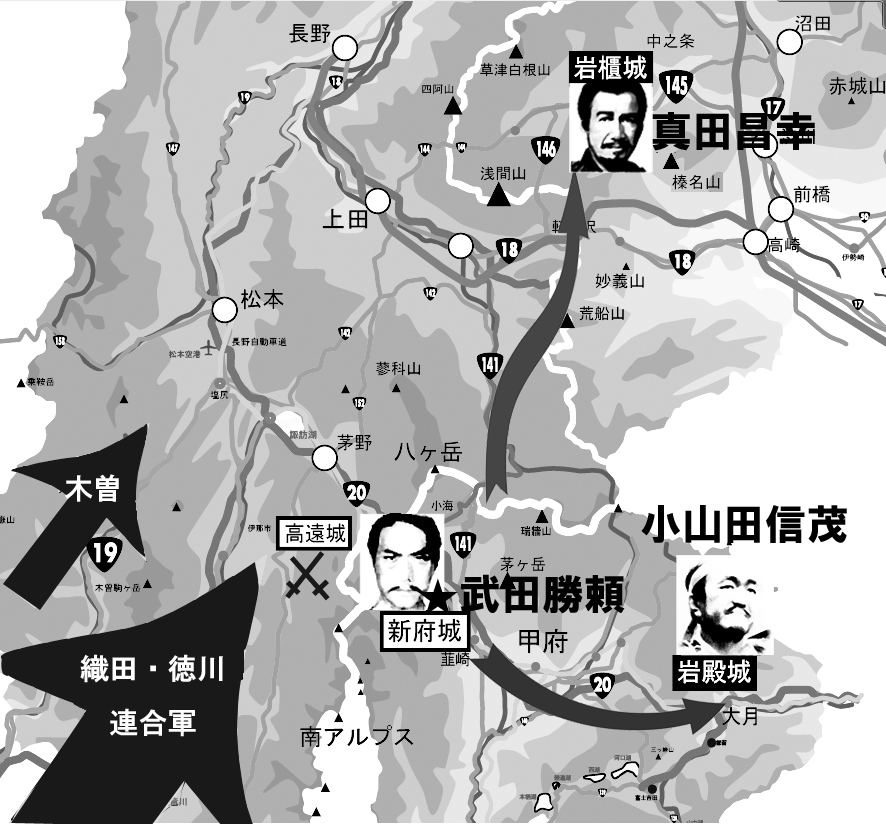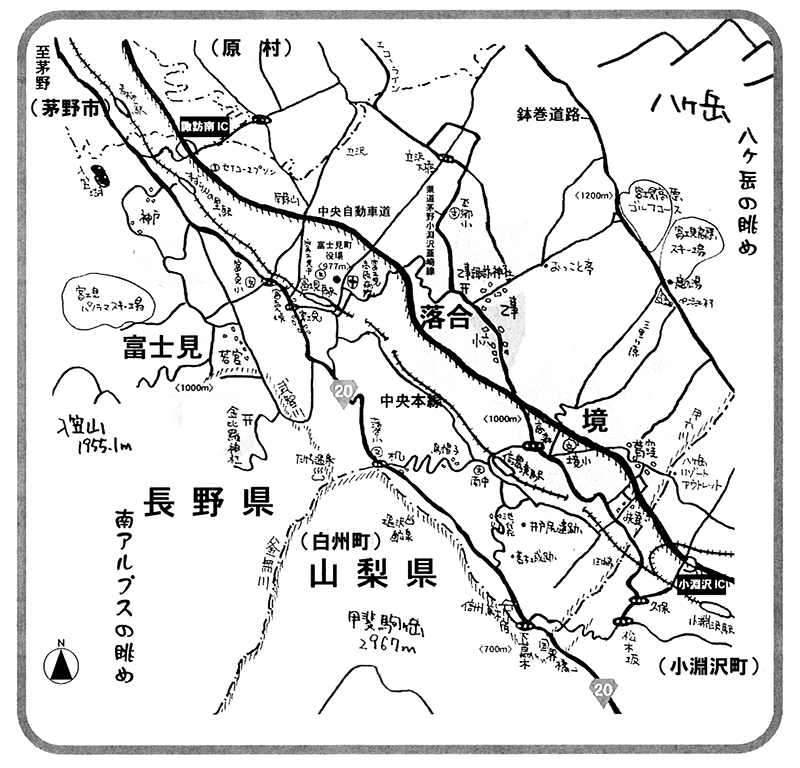▲ボテボテの醤油諸味に「手抜きがバレたかな~」と心が痛みました。
▲ボテボテの醤油諸味に「手抜きがバレたかな~」と心が痛みました。
11月15日 コンニャク作りイベントの準備
つくば市のお醤油屋さん「蔵元沼屋本店」の4代目店主である沼本さんが、今年も醤油絞りセット設置のため来て下さいました。諸味の入った桶から絞り、袋の中に移す作業をすぐ側で眺めていた私は、ボテボテの諸味を見て「手抜きがバレバレだねー」と言うと「そんなことないよ?」と慰めの言葉をくれました。
この諸味は一昨年5月、沼屋本店さんで仕込んだものを届けていただきました。それから二夏、自然に委ね、じっくりと熟成させるのですが、その間良くかき混ぜて空気を送り込み発酵のサポートが必要なのです。諸味を袋に入れ並べ始めると積み重ねた袋の重さで船口から「ツツツー」と醤油が滴る。それを見た時「あー、今年も釜あげうどんを振る舞うことができる」と安堵しました。
最初から圧力を加えると、袋が目詰まりしたり、澱おりが出てくるので、少しの間そのままにして置いてと言われました。しかしせっかちの私は明日までに多く溜まるように、と近くにあった砂糖2袋(2㎏)を上に載せてちょっとだけ重石に。すると船口から流れ出る醤油の量が変わりました。この頃になると部屋中醤油の香りが漂っています。
11月16日 コンニャク作りイベント 25人参加
朝のうち4℃とちょっと寒かったが集合時間近くになると、イベント日和の良いお天気になりました。集まった順にコンニャク芋を洗ったり、カマドを焚き付けたり、作業台の設置等手分けして準備しました。「サァー始まるよ!!」と声がかかると、コンニャク作り開始です。
「あれ?いつもと違う。何だろうね?」とつぶやくと、隣にいた人が「いつもは女性ばかりなのに今年は男性ばかりよ」と言いました。良く見ると、普段家に居る時台所に立つことが無いと思われる男性達が包丁を手に、危なっかしい手付きでコンニャク芋を切り刻んでいます。それをミキサーで滑らかになるまでかけ、その後ちょっとだけ放置し、鍋の中に入れて火を通します。
その間に凝固剤と水の入った容器を良く振って溶かします。コンロの上の鍋の中はアツアツですが、焦げないように良くかき混ぜていると、ねっとりと粘りが出て何となく透明になって来た時火を止めます。ゲル状になったものに、十分シェイクした凝固剤をまわし入れ、満遍なくかき混ぜ練り合わせます。この時、凝固剤の混ざらないところは固まらずに穴になってしまうので注意です。
 ▲これかな?いや~こっちだよ~!と安納芋を探しています。
▲これかな?いや~こっちだよ~!と安納芋を探しています。
その後箱に入れ冷めたら包丁で切り分けて、ゆがき水に浸してできあがりです。皆さんが自分のコンニャクを作っている間に、隣の焼魚用の土俵?では、串に刺されたニジマスが炭火でジワ~と焼かれています。その脇では、皆さんに焼いもを振る舞いたいと、サツマイモを持参した方がいて準備をしています。
専用のホイルに包み、あの手この手で何とか焼いもができつつある時「この中に安納芋があるよ?」と声をかけると、どれどれと集まって来ました。網の上には4種類のサツマイモがあるというが、どれが安納芋か分からない。皆はあれやこれやと迷っているが、私は迷わずそれらしきものに狙いをつけて取り、割ってみると、見事に的中です。(実はホイルに包む時お手伝いしたので形状で覚えていたので笑)
まるで宝クジに当たったかのように大喜びでほおばると、真っ黄色でねっとりと甘~くておいしーい!」と言葉少なになりました。「どの芋もおいしいよ?」と育ての親は言うけど、ブランド名に惑わされて??あれこれ迷っています。
 ▲今年は男性達が危なっかしい手付きでコンニャク芋刻みをやっています。
▲今年は男性達が危なっかしい手付きでコンニャク芋刻みをやっています。
焼いもの次はいよいよ絞りたて醤油をかけて食べる釜あげうどんです。茹でた生うどんに薬味(ネギ、カツオ節)を入れて船口から滴れ落ちる生の醤油を絡めて食べるのですが、これが絶品と大好評です。
「市販の醤油は食べる時に香を鼻で嗅ぎ、手作り醤油は飲み込んだ後、のどから香りが戻って来て鼻に抜ける」と沼尻さんが教えてくれました。これを釜あげうどんを食べている人達のそばで語ると旨さ倍増するのか、お代わりをする人もいました。
「魚焼けたよー」と声がかかると昼食です。旬のものや保存食品等で作った田舎膳ですが、普段口にしない素朴な料理をおいしいねーと喜んで食べて頂くと私も嬉しくなります。羽釜で炊いたご飯のお焦げに生醤油をかけて食べるとおいしいと、毎年お焦げを探して食べている人達がいます。それも御馳走のうちとか・・・。
和気あいあいと食べながらの情報交換に初めて参加した方は「楽しい一日でした」と言って下さいました。そして年末の餅つきには是非参加したいと言ってくれました。それを聞いて仲間が増えて嬉しいね?と近くにいた人達は喜びました。皆さんお疲れ様でした。(那須店 高久タケ子)
 ▲いつもの田舎膳で昼食です。
▲いつもの田舎膳で昼食です。