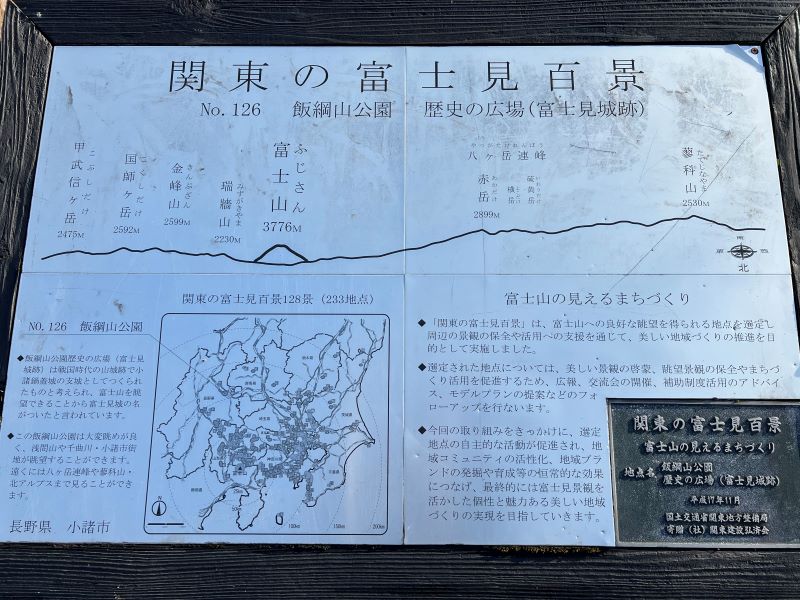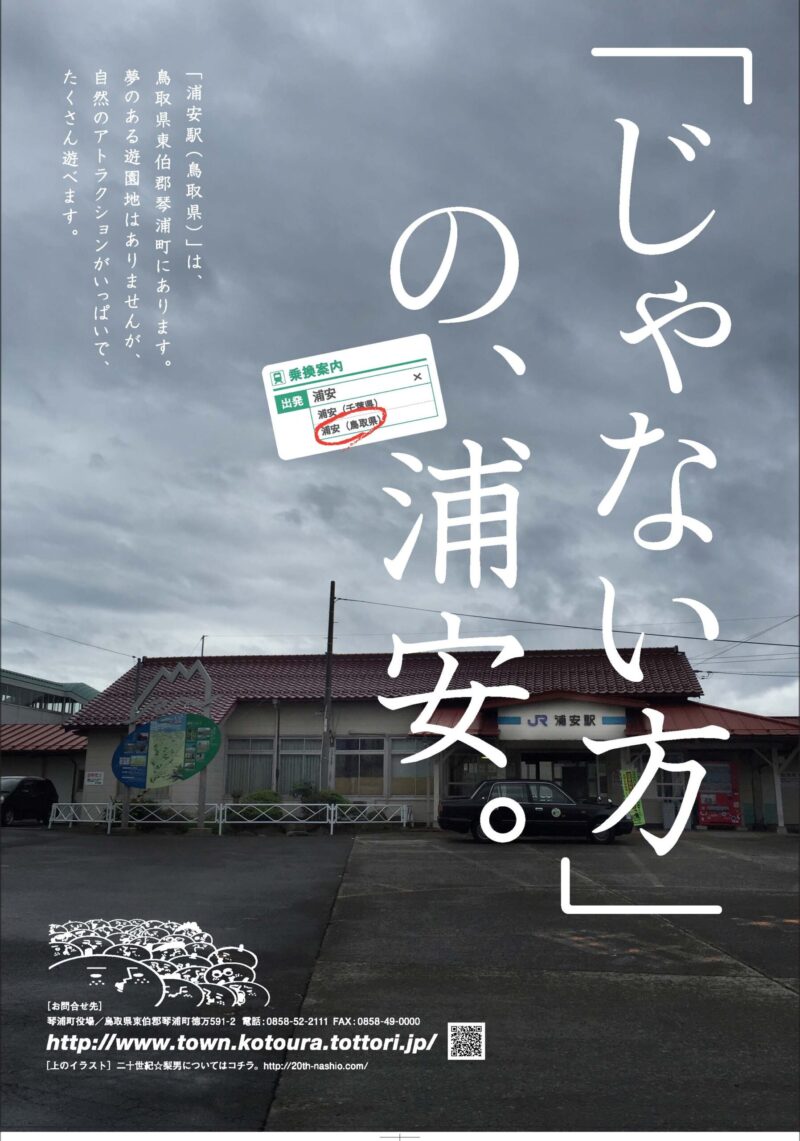▲酒田港⇔勝浦港は普段「定期船とびしま」にて運航されるが、船舶検査時には写真のように岩船港⇔粟島港で運航される「awalineきらら」にて代船運航される。
▲酒田港⇔勝浦港は普段「定期船とびしま」にて運航されるが、船舶検査時には写真のように岩船港⇔粟島港で運航される「awalineきらら」にて代船運航される。
日本海に浮かぶ島といえば、代表的なのは新潟県の佐渡島や島根県の隠岐諸島が挙げられるが、東北地方の日本海側にも島があることをご存知だろうか。
それが東北地方かつ山形県唯一の有人島であり、外周約10㎞に満たない小さな島、飛島だ。
島民約160人、平均年齢72歳、主な産業は漁業・旅館業と、瀬戸内海に点在する小島と同じ規模だが、離島自体が少ない日本海側ではかなり珍しい環境だ。
鳥海山の山頂が噴火した際に、日本海に山塊として飛び落ちそのまま島になったという伝説が島の由来となり、島の真東は酒田市ではなく秋田県にかほ市象潟町となる。
そのため山形県内では最も緯度が高いが、対馬海流の真っ只中に位置するため、意外にも山形県内のどの地域よりも平均気温が高い。
 ▲酒田港併設の「さかた海鮮市場」では朝獲れの新鮮な鮮魚が並び、決して観光地価格ではなく市民にも手頃な価格で販売されている。
▲酒田港併設の「さかた海鮮市場」では朝獲れの新鮮な鮮魚が並び、決して観光地価格ではなく市民にも手頃な価格で販売されている。
かつて北前船貿易により、最盛期は日本の商業の中心地と謳われたほどの隆盛を極めた酒田だが、この飛島も古来より佐渡島〜粟島との海の道が存在し、酒田港への潮待ち港としても機能した。
ただこの2島は新潟県佐渡市・岩船郡粟島浦村として単独行政を維持しているが、飛島は1950年に飽海郡飛島村から酒田市へと比較的早期に吸収合併されている。
村には小中学校があったものの、2019年3月に唯一の在校生が卒業してしまったことで、今や島内に子供たちの姿はなく、さざなみの音だけが聴こえてくるだけだ。
 ▲酒田港を出港すると雄大な鳥海山が見えてきて、地元の人たちが港にて見送ってくれる。
▲酒田港を出港すると雄大な鳥海山が見えてきて、地元の人たちが港にて見送ってくれる。
離島巡りに興味がある方には一度訪問を推奨するが、この島への公共交通機関は酒田市が運営する定期船のみで、特筆すべきは何とも言ってもその本数。
毎年4〜8月の大型連休等の繁忙期には1日2往復の運航だが、その他の通常期は酒田港09:30時発、勝浦港10:45着/13:45発、酒田港15:00着の僅か1往復のみ。
そのため日帰り観光では最大3時間滞在することが可能で、その他の時間帯に島内に留まるには、7軒あるいずれかの民宿に泊まる以外選択肢はない。
なお飛島は鳥海国定公園普通地域かつ第2種特別地域に指定されているため、キャンプが禁止されていることを念頭に置いて頂きたい。
そんな秘境感満載の飛島だが、島に訪れる方の大半は釣り目的で、その界隈にとっては日本でも指折りの釣り場のメッカとか。
逆に冬期は日本海が荒れるため1週間近くも休航になる時もあるため、文字通り絶海の孤島と化してしまう。
 ▲飛島西岸の賽の河原は切り立った断崖や、長年削られた丸石が転がっており、日本海の荒波を長年受け止めてきた自然の力を感じられる。
▲飛島西岸の賽の河原は切り立った断崖や、長年削られた丸石が転がっており、日本海の荒波を長年受け止めてきた自然の力を感じられる。
山形県といえば比較的内陸部の観光地が多いが、庄内地方には飛島の他に、酒田市の山居倉庫、鶴岡市の加茂水族館・湯野浜温泉・温海温泉と海側に面したスポットもあり、山岳信仰で知られる鳥海山・出羽三山も庄内空港や酒田・鶴岡駅を拠点として巡ることが出来る。
首都圏との移動は主に航空機がシェアを占めており、羽田発着のANA定期便が1日5便設定され、片道1時間5分と日帰りでも庄内観光は可能だ。
日本海の海の幸、平田牧場の山の幸、庄内米、酒田ラーメン、刈屋梨とご当地グルメも豊富で、食文化としても自給自足に特化した庄内地方。田舎暮らしの候補地として選択肢の1つにいかがだろうか。
※なお酒田市飛鳥という飛島に似た地名がありますが、こちらはJR羽越本線砂越駅が最寄り、合併前の旧平田町市街地にある全く別の場所です。(本部 髙橋瑞希)
 ▲標高約1350m。ゴツゴツした岩に囲まれた散策路。
▲標高約1350m。ゴツゴツした岩に囲まれた散策路。 ▲5月中旬~10月下旬頃に見られるヒカリゴケ。
▲5月中旬~10月下旬頃に見られるヒカリゴケ。