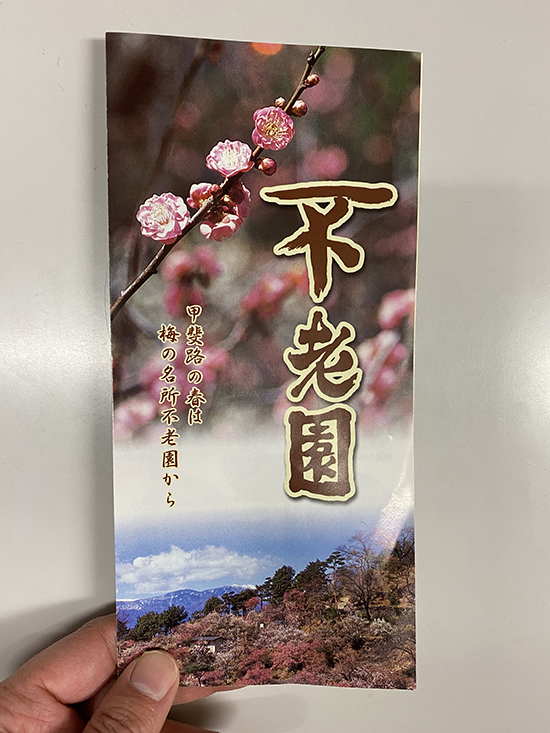▲田植えを終え、青々とした田んぼ。(北杜市高根町)
▲田植えを終え、青々とした田んぼ。(北杜市高根町)
6月を迎えました。
季節の変化を示す暦である「二十四節気」では、6月初旬頃を「芒種」と呼ぶそうです。日常では聞きなれない言葉ですが、読み方は「ぼうしゅ」、稲や麦などの穂の出る植物を蒔く時のこと。因みに、稲や麦などのイネ科植物の、先端の針状の突起を「芒(のぎ)」と言うそうです。
「芒種(ぼうしゅ)」も「芒」のどちらも私の知らない言葉で、「芒」は「すすき」とも読むそうです。暦を知る事は、私にとって昔からの営みを知る良いきっかけになりそうです。
北杜市は5月後半から6月初旬の芒種にかけて、田植えの最盛期を迎えます。「二十四節気」に大体あっていますね。ゴールデンウィークの頃に田んぼに水が入れられ、キラキラと輝いていた水面には、今、青々とした苗が整然と立ち並んでいます。風にゆれる様は見ているだけで、気持ちの良いものです。
田んぼから近隣の山々を見上げると、山頂の雪がほとんど無くなっています。6月は夏山登山の開始時期でもあります。
 ▲雨をうけ、生き生きとしたバラの花。(北杜市長坂町)
▲雨をうけ、生き生きとしたバラの花。(北杜市長坂町)
北杜市は北に八ヶ岳、南に南アルプスが位置し、特に八ヶ岳へのアクセス方法が豊富です。ルートも苔の森を楽しむ初級者向けのものから、ヘルメット着用が推奨の上級者まで様々。北杜市に住んだら、登山は身近なレジャーになることと思います。
6月は梅雨の時期でもあります。梅雨というと都心に住んでいた時は、蒸し暑かったり、暗かったりとあまりイメージが良くなかったのですが、ここ北杜市では若干イメージが変わりました。雨が降ることは変わらないのですが、なんというか暑いではなく、涼しい時の方が多い印象です。同じ雨でも気温が低いと、不快感がかなり減るようです。
 ▲梅雨の時期に咲くヤマボウシ。(北杜市大泉町)
▲梅雨の時期に咲くヤマボウシ。(北杜市大泉町)
そして一歩、お庭に出るだけで、さらに梅雨の印象は変わってきます。雨を受けたお庭の木々や花が生き生きとしているのです。雑草でさえも美しく感じてしまうことも。そういえば、物件の取材の際に、お庭の写真を撮るときは、炎天下よりも、小雨が降っている方が、魅力的な写真になります。日常生活にとって一見、面倒くさいと思う雨が、自然にとって恵の雨だということ。そんな当たり前のことに、改めて気づかされる北杜市の梅雨です。(八ヶ岳事務所 大久保 武文)
 ▲お庭の雑草も、雨で美しく感じる。(北杜市大泉町)
▲お庭の雑草も、雨で美しく感じる。(北杜市大泉町)




 ▲陸羽東線岩出山駅と構内の産直売場。
▲陸羽東線岩出山駅と構内の産直売場。 ▲息を飲む風景が広がる馬出し跡。
▲息を飲む風景が広がる馬出し跡。
 ▲池越しの「御改所」と室内。
▲池越しの「御改所」と室内。 ▲境界杭に「中新田町」の刻印。
▲境界杭に「中新田町」の刻印。 ▲中新田にある本庁舎。
▲中新田にある本庁舎。


 ▲遠く港が見える。
▲遠く港が見える。
 ▲仙台の牛タン。
▲仙台の牛タン。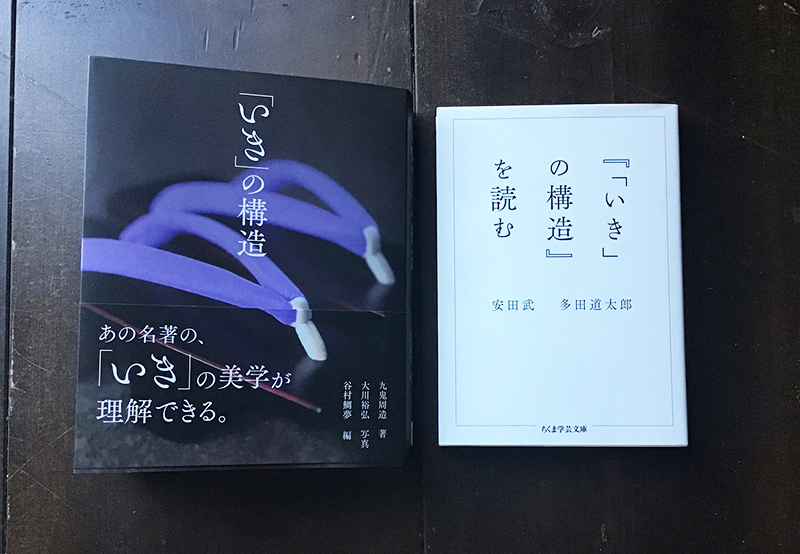











 ▲塩尻インター出口。
▲塩尻インター出口。