
▲『月刊ふるさとネットワーク』創刊号(1991年~2012年)の保存版。
わたしがふるさと情報館に入社したのは1995年のことだった。いまから28年ほど前になる。
その年の1月には阪神淡路大震災があり、入社の一週間前には地下鉄サリン事件が起こった。バブル崩壊後の景気後退は誰の目にも明らかで社会情勢も混沌としていた矢先のことだった。
そんな中、地方不動産を専門に取り扱うこの会社は常に時代の要請に応じてきたように思う。
会員向けの情報誌の毎月発刊と不動産実務、各地の団体と提携しながら都市と農村を結ぶ当社の基本的な姿勢は、インターネット全盛時代の今日、膨大な販売チャネルが拡散している中でも継続されているのだ。
===================
当時のエピソードを一つ。
ある百貨店が陶芸家の作品の展示販売をしている会場に我々も乗り込んでブースを出店した時のこと。
情報誌の購読会員を募ったものの、陶芸作品に興味ある方々であっても陶芸に適した田舎の場所探しをする人はいなく、結果的には一人の会員も得ることができなかった。
田舎探しは自分探し。人から勧められてやるべきものではなかったのだ。

▲「民話の里」岩手県遠野市に数多く残る見事な古民家。
そののち旺盛なエネルギーを持つ会員の方々によってわれわれの提唱するグリーンツーリズムが評価され、毎日新聞社本社の「グリーンツーリズム大賞」に選ばれ表彰された。
それは「ラーバニスト※」のみなさんの勝利でもあった。

▲中山道の古き街道文化を感じる長野県佐久市の日本家屋。
その前後に当社が中心となって全国に広がりつつあった利用されない古い日本家屋を現代に蘇らそうという、民家再生の全国組織(NPO日本民家再生リサイクル協会・現 認定NPO日本民家再生協会)が生まれその理事長には日本文化の伝統を継承する観世流の能役者が選出された。
この反響はすさまじく、社内の電話は数日間止むことがなかったほどだった。
「実家」の問題がマスコミによってクローズアップされ出すとNHKの取材班が山梨県北杜市の物件を取材に来るなどその対応に忙しい思いもしたし、「空家等対策特別措置法」が成立されるやいなや(2014年、平成26年11月)、空き家活用法の事例紹介で大学の市民講座や宅建協会の地方支部などで登壇したこともあった。
自治体の「空き家バンク」ではその立ち上げとともに地方移住やいわゆる二地域居住の実務、東京のふるさと回帰支援センター等で行われている相談会や協議会等の要請を受け、いま現在もリアルやリモートで参加させていただいている。

▲文化放送第7スタ。「大人ファンクラブ」毎週土曜日6:25~。(中村の放送回は毎月第4週目)
わたしの八ヶ岳事務所が所属している山梨県の官民協同組織「やまなし二地域居住推進協議会」(通称「甲斐適生活応援隊」)でも県内の自治体に応募して活躍する多くの地域おこし協力隊のメンバーたちとも知り合うことができた。
バブル崩壊→震災→実家のあり様→民家再生→空き家バンク→移住定住→二地域居住と、地方不動産を扱う我々の日常とそれを取り巻くキーワードは常に変化してきた。そしてコロナを経験した都市住民の地方志向はリモートワークとメディアの多様化等により今後さらに加速化していくことだろう。
さらには「少子化対策」としての田舎暮らしがこれからの新たな潮流として拍車をかける勢いだ。
そして昨年末の政府発表では、東京集中是正へ支援拡充との方針から、2023年度の地方移住支援金として次のことが挙げられている。
1、地方での起業に300万円
2、地方での就職に100万円
3、子供一人当たり100万円を追加
ただし、現在東京23区居住者か東京圏から23区への通勤者限定で、移住後5年間は居住するという条件がつけられている。
自治体によっては中古物件を購入する場合に購入補助金として100万円程も出る(金額はそれぞれ違います)。

▲甲府盆地の東側に位置する山梨県山梨市。文化財級の古民家が残り、それらを大切にする工務店や設計事務所など熱意も高い。
楽しみながら古家をリノベする方々も増えてきておりその過程を自ら情報発信している。動画サイトでも閲覧回数は軒並みうなぎ登り。そうした大きな社会の変化やうねりの様なものを肌で感じられるのが、実はこの仕事の醍醐味でもある。
我々はこれからも多くのラーバニストに支えられながら事業を続けていきます。そして3年ぶりに6月から各地で「現地見学会」を開きたいと考えていますので、みなさまどうぞリアルでご参加ください。(代表取締役 中村健二)

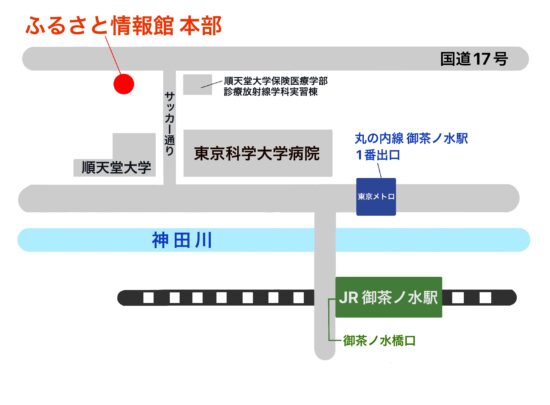












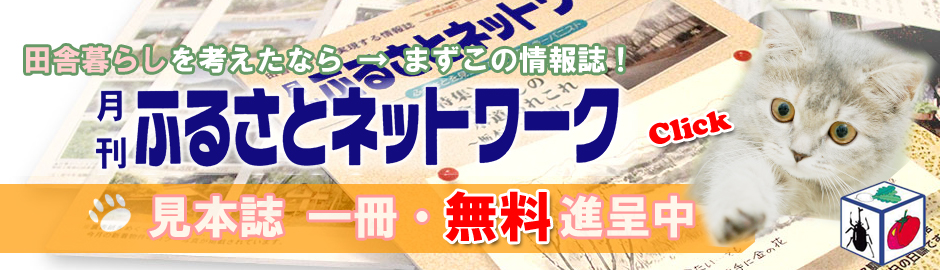
 ▲遠野ホップ収穫祭で販売された遠野パドロンフリット。
▲遠野ホップ収穫祭で販売された遠野パドロンフリット。
 ▲吉田代表と共に奮闘する奥さんの美保子さん。収穫中です。
▲吉田代表と共に奮闘する奥さんの美保子さん。収穫中です。


