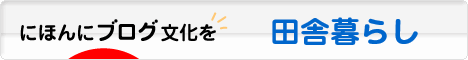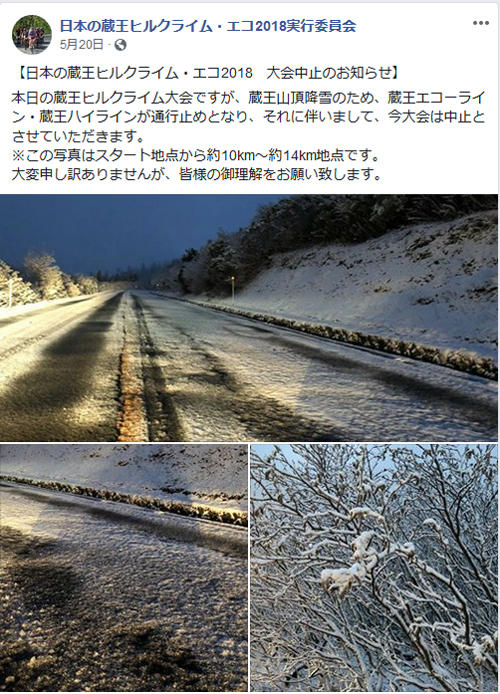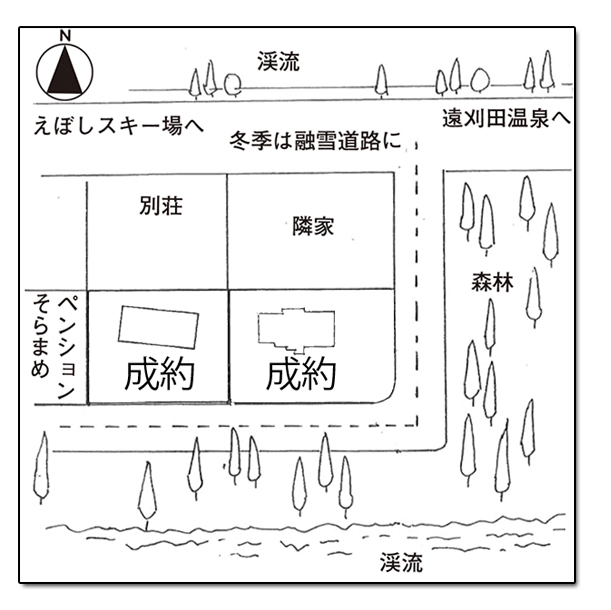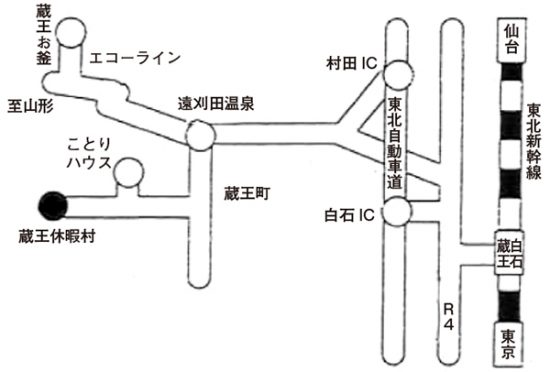6月13日 フキ採り
毎年のことですが、6月に入ると私の中に漫そぞろ心が湧いて来ます。それは大好きな「フキ採り」の楽しみが到来するからです。旬の宝物が待っている場所は、マウントジーンズ那須スキー場に行く途中で、昔は桑畑だった所です。
養蚕をやめて何十年も経った桑の木は、見上げるほどの大木になり、雑木林のようなその中に木漏れ日を浴びて育っています。この土地の持主は私の母の知り合いで、昔は6月に入ると、母に「フキ採り」のお供を求められたものでした。いつの間にか受け継ぐかの様に、あの頃の母とまったく同じ事をやっている自分にふと気付くことがあります。

今まで採りに来ていた人達が今年は誰も来ないということで、手付かずのフキの群生を目の前にして「採り放題」に気合が入ります。採り始めると「あれ?穴ボコがない」と昨年と違うことに気付きました。昨年はあちこち穴ボコだらけで足元が危なかったけど、今年はとても楽です。この穴ボコは、フキの中に共生している山ユリの球根を狙ってイノシシが出没するせいとか…。
数年前、この穴ボコを見つけた時、あまりにも上手に沢山掘られていたので、「ユリ根ドロボー」と駐在所に盗難届を出したらしい。その後ハンターが来て犯人はイノシシと知らされたとか・・・。その話を聞いた時、「イノシシと鉢合わせ?なんてことになったらどうしよう~」とちょっとだけドキドキしていましたが、フキ採りの欲の方が勝って、いつの間にか忘れていました。
約2時間くらい過ぎた頃、「もう帰ろうか~」と採ったフキを集めると、驚いたことにお友達2人と私で約35㎏も採れていました。
車まで約30mくらいを背負って運び出すわけですが、途中、野菜畑に村の人らしい男性が農作業をしていました。
「イノシシの被害はありますか?」
と声をかけると、
「今年はまだ来ないけど昨年は楽しみにしていた新じゃがいもをひと晩で荒らされてしまった」とか。
「あいつらは家族ぐるみで来るんだから堪らないよな~」とぼやいていました。
持ち帰ったフキは半分キャラブキにし、あと半分はちょっとゆがいて皮をむき塩漬け保存にし、イベントの時に田舎膳の一品に使います。
 ▲とっても良く仕上がったキャラブキ。冷凍保存でイベントの時の一品にします。
▲とっても良く仕上がったキャラブキ。冷凍保存でイベントの時の一品にします。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
7月28日 暑気払い(16人参加)
「災害級の猛暑」と連日報道のある日、「土用のウナギいつやるの?」と数人の方から問い合わせがありました。今年も「ウナギ高い!」とかいってるけど、連日の暑さでバテ気味の体に滋養の御褒美という名目で催すことになりました。
夕方、那珂川町の「高瀬やな」まで片道1時間かけて買って来た「ウナギの白焼き」が届くと、俄かウナギ屋が開店します。ウナギの串刺しが始まると、「去年と同じ値段にしてくれたっていうけど、本物のウナギを食べられて有り難いね~」と感謝です。
「高瀬やな」で串の話をすると、ウナギ用の串をサービスしてくれたそうで、その串を使うと、「この串はしっかりしていて刺し易いよ~」と終る頃には職人級?の手捌きになったとか。いつもは外の炉で焼くのですが台風12号が来るというので、今回は囲炉裏で焼くことになりました。
 ▲「おお~!今年の串は刺し易い」と喜ぶ串刺し職人達。
▲「おお~!今年の串は刺し易い」と喜ぶ串刺し職人達。
もちろんウナギは炭火で焼きます。落下防止の金網の上に金属の棒を渡しその上に串刺しのウナギを並べて、パタパタとウチワで煽るその姿は「ウナギ屋のオヤジ」そのものになりきっています。ウナギを焼いている煙と匂いが漂う頃になると「そのまま」とか「三度つけ焼き」とか好みを言い始めたので、とり合えずそのまま一串づつ渡しました。
 ▲俄かウナギ屋のオヤジ。カッコ良かった~。来年もお願いします。
▲俄かウナギ屋のオヤジ。カッコ良かった~。来年もお願いします。
カンパイの後、私は一度つけ焼きで食べましたが、脂がのっていて飲み込んだ瞬間に五臓六腑に染み渡り、ちょっとだけ元気になった様な気がしました。
「今年の夏はもう一度食べないと体がもたないね~」といいながら、バテ気味の体へ滋養強壮の御褒美を口に運び「幸せ」をかみしめました。 (那須店 高久 タケ子)
 ▲ウナギを食べて猛暑を乗り越えよう~?とカンパイ。
▲ウナギを食べて猛暑を乗り越えよう~?とカンパイ。
↓↓↓栃木・那須物件一覧はこちら↓↓↓