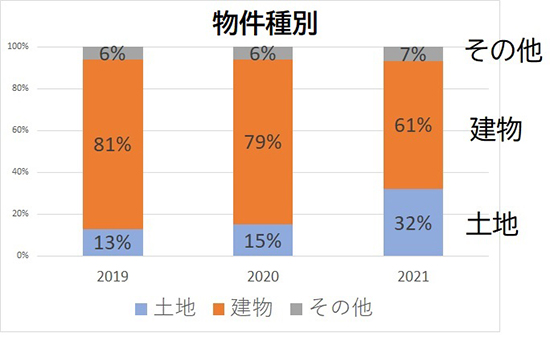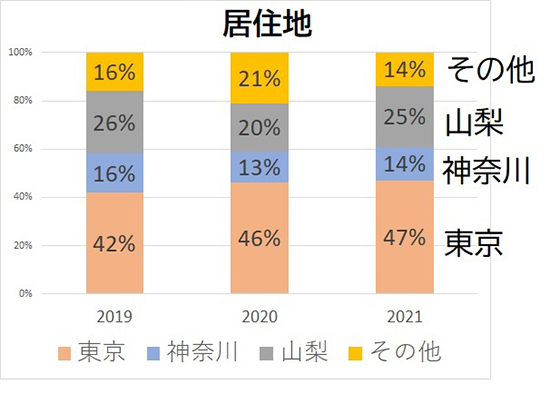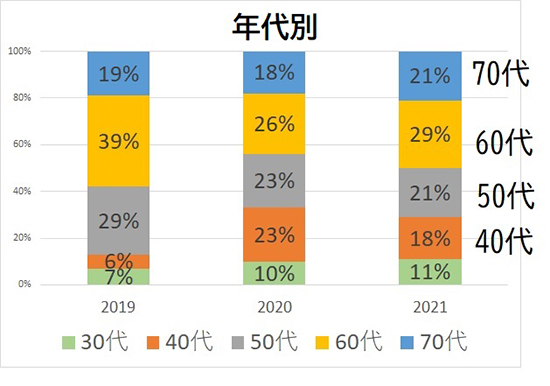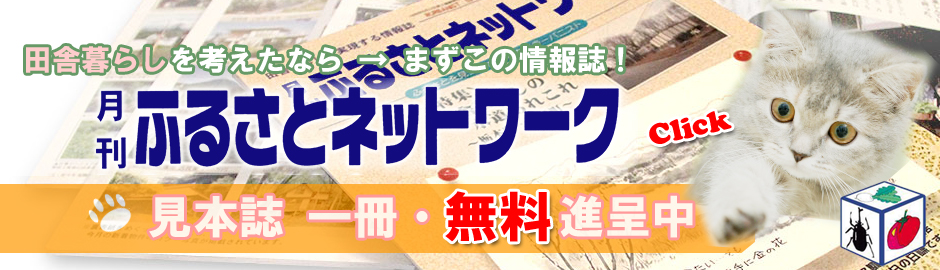▲黄金色の田んぼ。(北杜市高根町)
▲黄金色の田んぼ。(北杜市高根町)
9月に入ると北杜市では一足早く秋の雰囲気を感じるようになります。暑さから涼しさへと変わる月といえるでしょう。2021年の気象庁の記録を調べると、9月に入ると最高気温が30度を切ってきます。ただ、それよりも体感に大きく影響するのが、最低気温の変化でしょう。最低気温が20度を切り、日によっては15度、10度近くまで下がることも。
8月と同じ服装では過ごせない時間帯が多くなってきます。大変すごしやすい季節となりますが、同時に夏が終わってしまった寂しさも覚え、9月後半にはそろそろコタツを出そうかなんて思うことも。気温の変化には気を付けないといけない季節です。
■保険について
私的な事ですが、山岳保険の更新時期が近づいています。山岳保険は登山をする人にはポピュラーですが、一般的には余り知られてないかもしれません。登山を始めるときに、まずケチらずに購入しないといけないのが登山靴とレインウェア。次に速乾の衣類、登山リュック。専門のものを揃えると登山が快適になり、身体の負担が一気に軽くなります。
ただ、本当に大事なところは安全性の確保です。登山靴を使わなければ、足を捻って歩けなくなるかもしれません。レインウェアが無ければ、急な雨により、服が濡れ、急激に体温が奪われ、低体温症で動けなくなるかもしれません。街であれば、お店で一休みできるのですが、山の中ではそうはいきません。命を守るために、きちんとした道具を揃えていかないといけないのです。
そしてその次に出てくるのが山岳保険です。どんなに道具を揃えても、注意をしていても、強風や浮石でバランスを崩したり、足を滑らせて、ケガで歩けなくなったり、滑落してしまう事があるかもしれません。そんな時にお世話になってしまうのがヘリや救助隊による捜索です。
 ▲救助ヘリ。できればお世話にならないことが一番ですが、
▲救助ヘリ。できればお世話にならないことが一番ですが、
万が一の緊急事態には心強い隊員の方々に感謝。
命をかけた大変な作業なので、救助隊の日当、宿泊費、ヘリ整備費と自然と費用も大きなものになります。YAMAP 登山保険のページによると、ヘリ捜索費用が約165万円、救助隊の費用が約45万円という試算が出ています。
無事に救助いただいても、日常生活に影響が出るほどの金額です。この捜索費用を補償してくれるのが山岳保険です。1泊2日など日にち単位でも契約できますが、私は1年間の契約で入っています。
加入しているのは、モンベルの野外活動保険というもので捜索救助費用が500万円まで。保険金額は年間3190円。捜索救助費用に目的を絞った割安なプランです。
事故にいつ出会うのかは誰にも分からない。登山を楽しむ上で、もしもの金銭的なリスクを低減してくれる、有難い保険です。
(八ヶ岳事務所 大久保武文)
 ▲雨の中の登山。そこに山がある限り・・・。(白駒池・丸山の苔の森)
▲雨の中の登山。そこに山がある限り・・・。(白駒池・丸山の苔の森)
==============================
🌸ふるさと情報館では、八ヶ岳南麓に広域に広がる山梨県北杜市の物件は、物件数の多さ、地域の特色、アイデンティティを考慮し、馴染みのある町村名(旧町村)で表記しています。
【八ヶ岳事務所エリアの物件】
・八ヶ岳南麓エリア・・・北杜市高根町、北杜市長坂町、北杜市大泉町、北杜市小淵沢町
・韮崎・茅ヶ岳エリア・・・北杜市須玉町、北杜市明野町、韮崎市、甲斐市
・武川・白州エリア・・・北杜市白州町、北杜市武川町
==============================




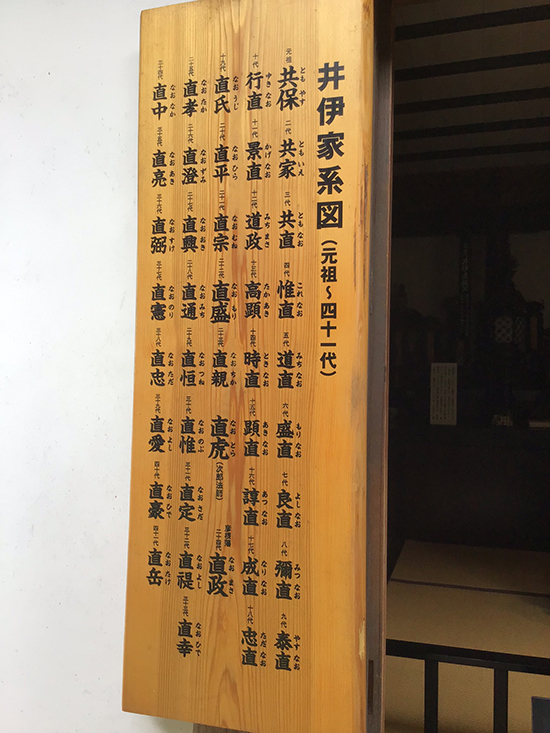





 ▲シンプルで美味しい「焼き野菜」。
▲シンプルで美味しい「焼き野菜」。
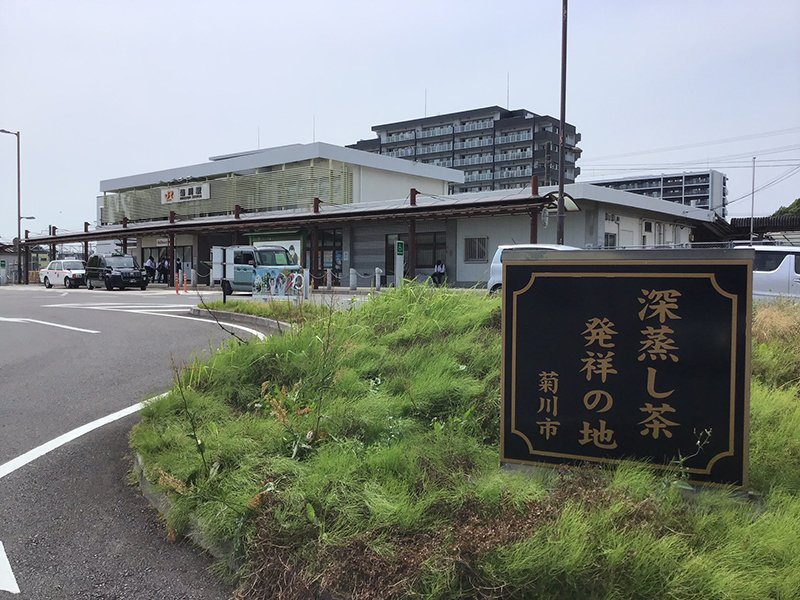

 ▲馬場。
▲馬場。
 ▲矢島屋書店入口。デザインは鯨を模したもの。
▲矢島屋書店入口。デザインは鯨を模したもの。


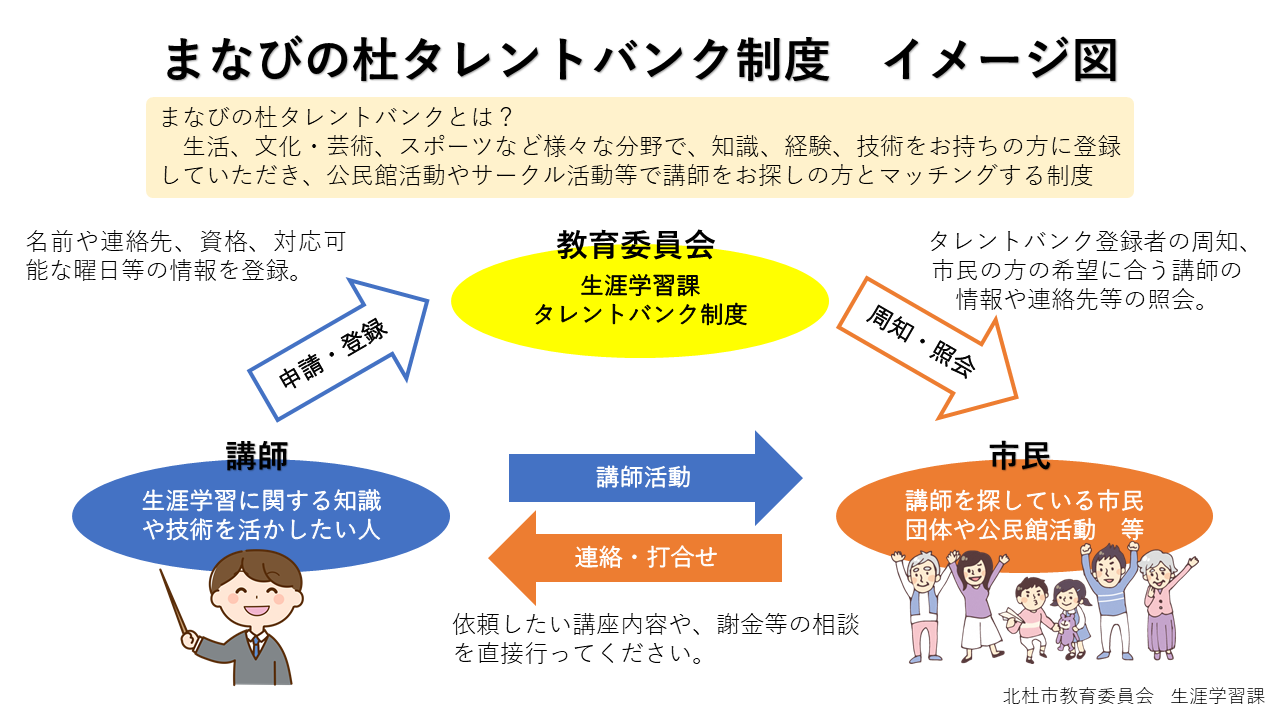 (※北杜市役所HPより)
(※北杜市役所HPより)