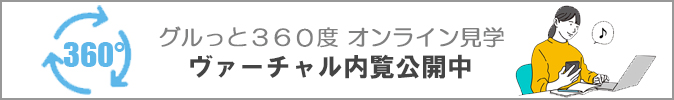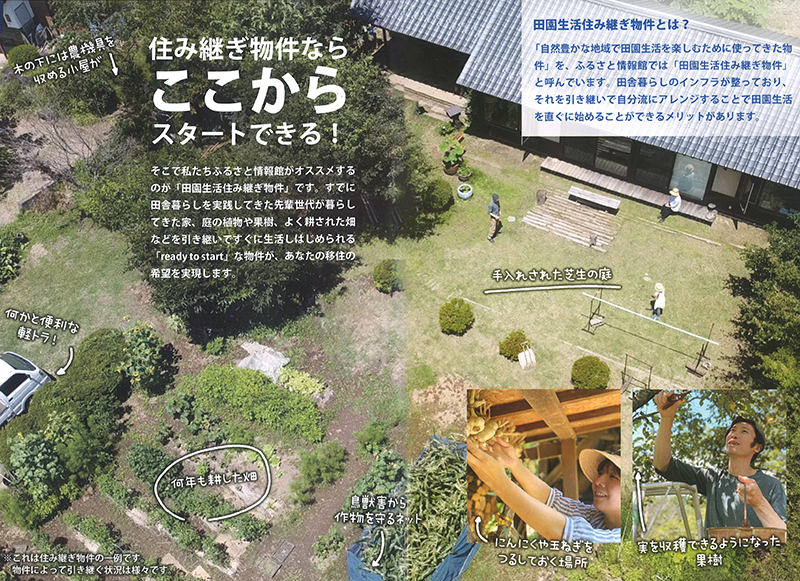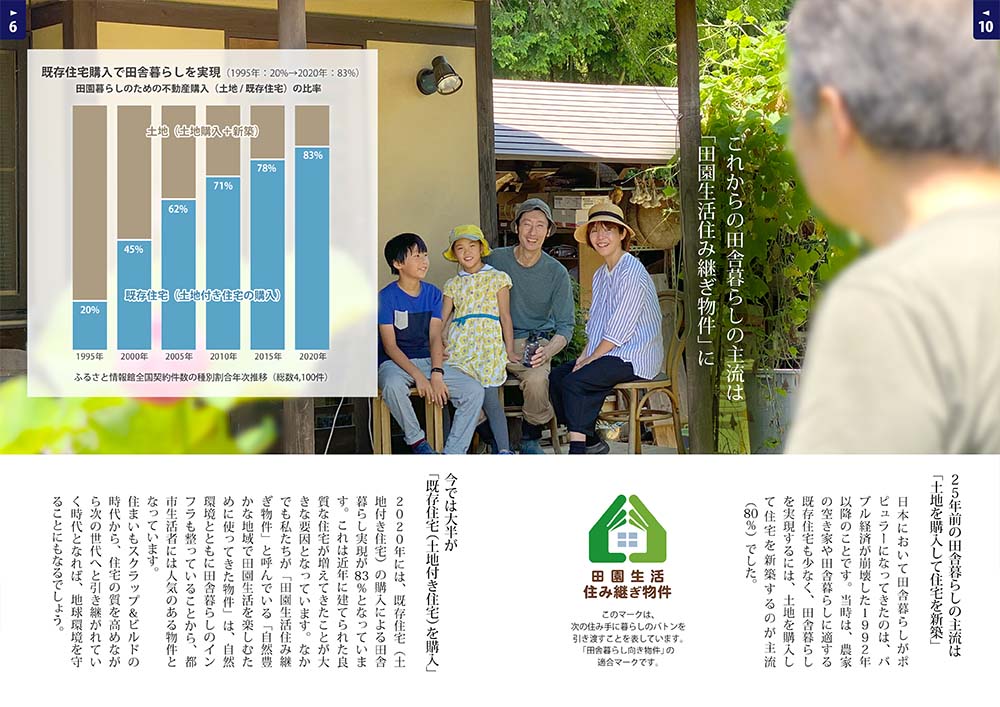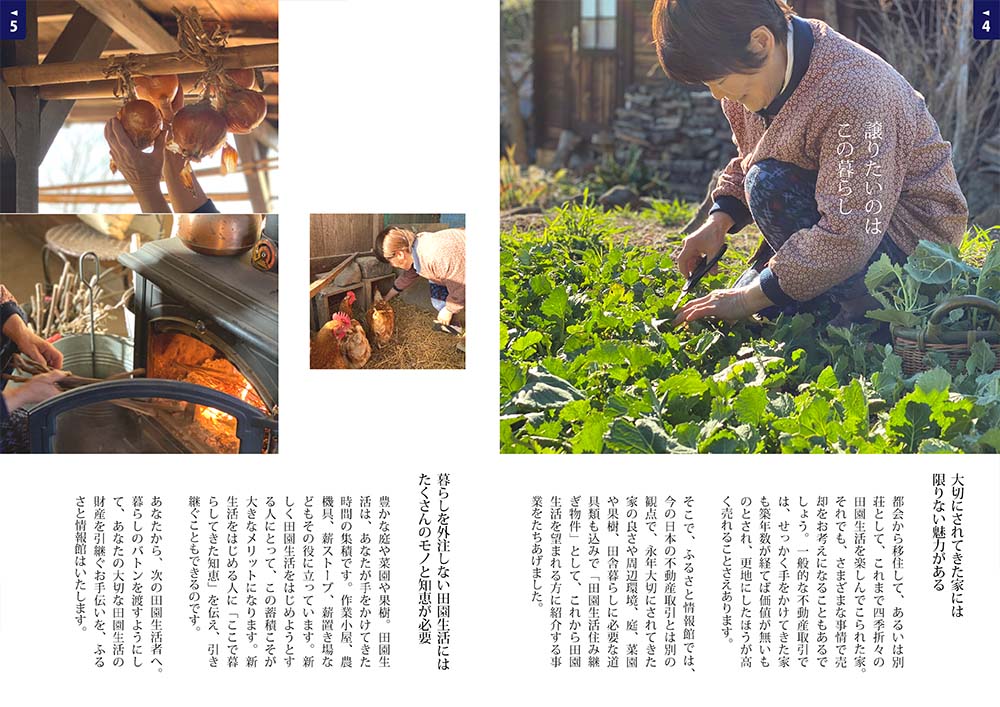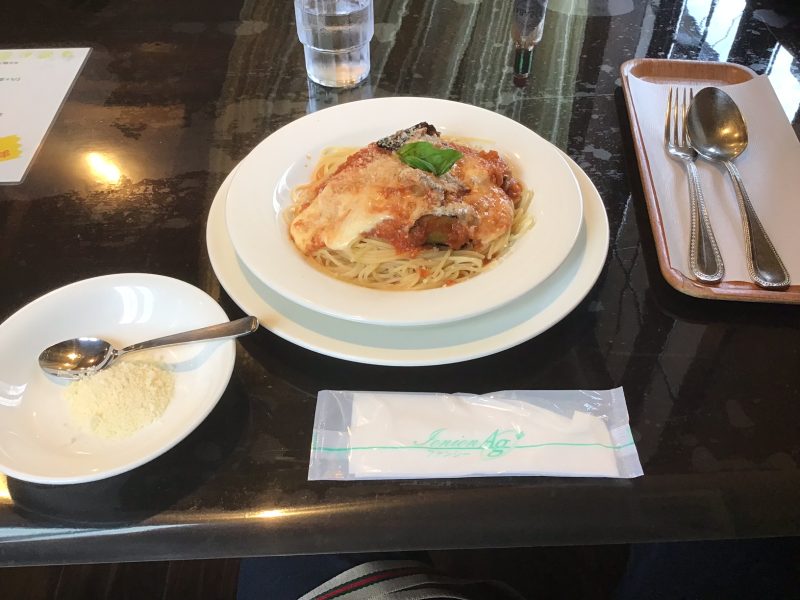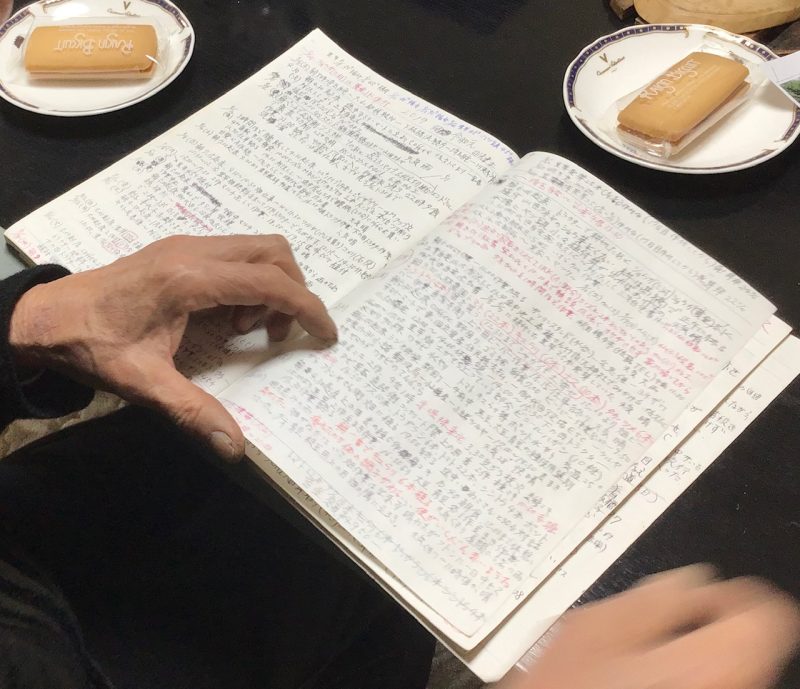▲再建された陸前高田市立博物館。
今回訪れたのは陸前高田市立博物館。
2011年の津波により被災した「旧市立博物館」と「海と貝のミュージアム」の展示物や資料を多くの人の努力と情熱により再生修復、建物は新しい市街地に再建され、昨年11月5日にオープンした施設です。
入館料はなんと無料。
入り口のパンフレットを手に取り館内を歩き最初にたどり着いたのは〝大地の成り立ち〞のコーナー。1850年に落下した〝気仙隕石(けせんいんせき)〞の標本と共にプロジェクションマッピングによる映像と音の見事な演出。
遠野からそう離れていない土地であっても知らなかった歴史や成り立ちを、臨場感をもって学ぶ事が出来ました。
〝奇跡の海三陸〞のコーナーでは陸前高田の生態系が、多くのはく製などの目で見て楽しめる展示がされていました。
〝宿命とともに生きる〞のエリアでは津波の歴史と教訓が紹介されており、私たちの知る東日本大震災もその長い歴史の資料の一つに加えられていました。

▲博物館屋上の展望デッキより。太平洋や防潮堤、新旧道の駅などが見渡せる。
他にも館内には資料の修復の様子や博物館復活まで道のり紹介、お子様向けの体験コーナー等もあり、家族で楽しめる施設になっていました。
皆さんも新しい拠点を探す際、博物館や歴史館などで歴史をのぞいてみるのも良いかもしれませんね。(みちのく岩手事務所 佐々木敬文)
========================================
陸前高田市立博物館
住所:岩手県陸前高田市高田町字並杉300番地1
TEL:0192-54-4224
開館時間:午前9時00分から午後5時00分まで(最終入館は午後4時30分まで)
休館日:毎週月曜日(祝日・休日の場合は翌日)
12月29日から翌年の1月3日まで
観覧料:無料(特別展示を行う場合は、展示内容に応じ観覧料を徴収する場合があります)
※詳細に関しては、陸前高田市ホームページ内の博物館ページ(https://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/soshiki/kanrika/hakubutsukan/index.html)をご確認ください。