
仙台から真北方向へ60キロほどの場所にある「大崎市・岩出山(いわでやま)」と音響効果にすぐれているといわれるバッハホールのある「加美町(かみまち)」の話である。なかなか味わい深い場所であるので今回ご紹介させていただくことにした。
岩出山城は伊達政宗公が天正年間から慶長年間の12年(10年という説もある)を過ごした断崖絶壁の城である。24歳から35歳のころだ。いまでいう人生の節目に当たる年だともいえる。

その後四男が後を継ぎ岩出山伊達家が誕生したといわれる。馬出しのあった場所からは市街地、江合川(えあいがわ)そして名峰・栗駒山(標高1626m)を望むことができる。本丸跡を下って行けば1キロほどで『有備館(ゆうびかん)』に着く。
『有備館』とはなにか。江戸時代の伊達藩家臣である岩出山伊達家が開設した学問所で、郷学と呼ばれる。中国故事の「備え有れば憂いなし」がその出典だ。開校は幕末の嘉永3(1850)年頃と考えられるという。現存する『有備館』の建物と池を見るには入場料(350円)が必要だが、一見の価値ありだ。
 ▲陸羽東線岩出山駅と構内の産直売場。
▲陸羽東線岩出山駅と構内の産直売場。
隣接した「東北の駅百選」の有備館駅構内には「伊達政宗公騎馬像」がある。この像はもともと仙台駅にあったもので2008年にこの場所に設置された。(日付とは関係なくウソではありません。)
伊達様のお城下から丘陵地帯へ。県道を走るとすぐに雑木林の疎林を尾根づたいに道路を進むことになる。途中、国立音楽院の宮城キャンパスの脇を抜けた。昨年の11月にはバッハホールでウインターコンサートも開かれていた。大崎市から加美町に入ったのだ。
 ▲息を飲む風景が広がる馬出し跡。
▲息を飲む風景が広がる馬出し跡。
「加美町」は「群馬県甘楽町(かんらまち)」と同様、非常にきれいな町名だが、神の宿る場所を表すといわれる「賀美郡(かみごおりぐん)」に由来するらしい。そして町の中ほどに聳(そび)え立つ独立峰の「薬莱山(やくらいさん)」(標高553m)は町のシンボルとして「加美富士」とも呼ばれている。
ところでこの町の「中新田(なかにいだ)」を私は「なかしんでん」と言うのだと勘違いしていた。静岡県には御前崎に「池新田(いけしんでん)」というところがあるためだが、女優の「新垣(あらがき)さん」を「にいがきさん」とずっと思い込んでいたように読み方は難しい。

 ▲池越しの「御改所」と室内。
▲池越しの「御改所」と室内。
宮城県の中西部に位置する加美町は570平方キロの町域に27800人(推計人口)が暮らす(2022年3月1日現在)。内陸性の気候のため寒暖差が大きく積雪量もやや多めのようだ。ただし下多田川あたりの尾根沿いの別荘地でも町では除雪してくれるようだ(町建設課に確認)。
 ▲境界杭に「中新田町」の刻印。
▲境界杭に「中新田町」の刻印。
町の東西を国道347号線(中羽前街道)、南北を国道457号線(羽後街道)が走り古くから交通の要衝地であった。ここからどこへでも出られるというのはちょうど、岩手県の「遠野」に似ている気がした。山あいの雑木林あり、牧場あり、農地ありの田舎道はどこかほっとする場所だ。
空き家バンクの登録物件を見てみよう。宮崎支所や小野田支所など町場が中心で、別荘地はほとんどない。丘陵地と田園の近接したところで移住者が農業を始めており町の活性化に一役買っている。さらに東北自動車道古川インターに向かうバッハホールのある辺りは精密機械工場が集積しており、大崎市と並んで一大精密機械産業都市としての顔を持つ。
 ▲中新田にある本庁舎。
▲中新田にある本庁舎。
30万都市圏の一翼である岩出山から加美町はいまもなお、伊達藩の進取の気性と渋みを受け継ぎながら「備え有る」まちづくりを目指しているように思えた旅であった。(宮城・岩手・秋田担当 中村健二)
 ▲甲府盆地の東縁に位置する旧牧丘町。明るい高台の立地で田舎暮らしの人気エリア。
▲甲府盆地の東縁に位置する旧牧丘町。明るい高台の立地で田舎暮らしの人気エリア。 ▲甲府盆地・ドローンで撮影した富士山。
▲甲府盆地・ドローンで撮影した富士山。 ▲子供でも操縦できる容易さがドローンのウリだが、風に弱いのが弱点だ。
▲子供でも操縦できる容易さがドローンのウリだが、風に弱いのが弱点だ。












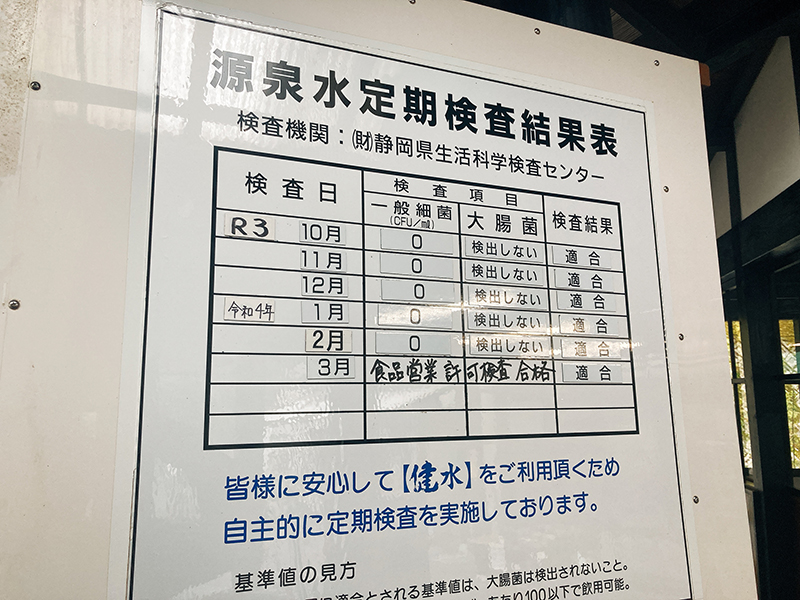
 ▲こちらは大沢里集落の中にある昔からの水場。
▲こちらは大沢里集落の中にある昔からの水場。







 ▲雨をうけ、生き生きとしたバラの花。(北杜市長坂町)
▲雨をうけ、生き生きとしたバラの花。(北杜市長坂町)



 ▲陸羽東線岩出山駅と構内の産直売場。
▲陸羽東線岩出山駅と構内の産直売場。 ▲息を飲む風景が広がる馬出し跡。
▲息を飲む風景が広がる馬出し跡。
 ▲池越しの「御改所」と室内。
▲池越しの「御改所」と室内。 ▲境界杭に「中新田町」の刻印。
▲境界杭に「中新田町」の刻印。 ▲中新田にある本庁舎。
▲中新田にある本庁舎。