 ▲ペンション外観。四季を通じて観光客の絶えないのがここ蔵王。
▲ペンション外観。四季を通じて観光客の絶えないのがここ蔵王。
宮城県蔵王町 ペンション1900万円
このコーナーで営業物件を取り上げるのは初めてのことだと思う。「蔵王町」は言わずと知れた東北屈指の温泉リゾート地で、宮城県南に位置しており152平方キロメートルの町域に1万1千人が暮らす。「蔵王連峰」の東南側にひらけた地形で松川の河岸段丘が作り出した強固な岩盤の下から湧く良質の温泉が自慢だ。
コロナ前の2014年の町の観光協会資料によれば、年間の入り込み客数は177万人ほどだという。仙台市内からは約45キロで1時間もかからない。スキーや温泉、日帰りドライブ、グルメ、こけし土産のほか森林浴や健康増進など一年を通じて手軽なリゾート地として人気がある。
 ▲赤茶けた排水溝からは湯煙が立ち昇っている。
▲赤茶けた排水溝からは湯煙が立ち昇っている。
課題は地域の高齢化と若年層の流出だが、蔵王町は移住政策の取り組みにも積極的だ。ペンションオーナーも徐々にではあるが代替わりしているという。そのペンションの数は20件がリストアップされており、本物件はそのサイトでも上位にランクされている。場所は「蔵王の御釜」に行くエコーライン入口の分譲地の最奥にあり、雑木林のなかにたたずむ静かで落ち着いた環境も自慢のひとつだ。
オーナー夫妻はお隣の山形県のご出身。わたしが初めて蔵王の御釜に行ったのは実に40数年前の高校2年の秋だった。新幹線は当時まだ無く、「奥入瀬渓谷」から観光バスでひたすら南下し、寒さに震えながらみどり色の御釜を奇跡的に30秒ほど見ることができたのだった。
その後、一昨年の3月に今回とは別のペンションの売却相談のあとに訪れたのが2度目。このときはエコーラインがまだ冬季のため開通しておらずスキー場のところで引き返してきた。そして今回が3度目ということになった。
 ▲田園の先にある蔵王連山は黒い雲に覆われていた。
▲田園の先にある蔵王連山は黒い雲に覆われていた。
そのペンションのオーナーいわく、「エコーラインは積雪のため今日は通行止めよ。残念だったわね!」道路看板では「11月5日から封鎖」と案内が出ていた。もしかしたら、善良なる市民のために特別に開いているのではないか。まだ紅葉も始まったばかりだし、雪なんか積もるハズがない。そんな淡い期待を胸にわたしの四駆はヘアピンカーブをひたすら登る。
スキー場の先のゲートは閉まってはいなかった。どうだ、と内心ほくそ笑む。わたしのほかにも上がって来る車は多い。勇気をもらうようにわたしもさらに高みを目指す。するとどうだ。路肩には雪が積もり始めているではないか。
 ▲エコーライン入り口の大鳥居。
▲エコーライン入り口の大鳥居。
気温はまたたく間に2度まで下がった。氷点下までもわずかだ。キツいカーブを過ぎ、蔵王寺の先にはトイレ休憩できる駐車場があった。ゲートはここで閉ざされていた。
残念ながら今回はここまで。しかしながら、次々に登ってくる車が後をたたない。駐車場内にも積雪がある。午後になればさらに気温は低下する。ちょうどいまが潮時なのだ。
 ▲またしても御釜の展望台を前にしてU ターン。
▲またしても御釜の展望台を前にしてU ターン。
それにしても多くの人が「行けるところまで行ってみたい!」という心理や気分はとても分かる気がした。これまで緊急事態で押さえつけられていた日常からいっきょに枷が外れたように、、、人々の情熱がそれこそ堰を切ったように溢れ出してきているのである。
「八ヶ岳」でも清里の先にJR最高地点という場所(標高1375メートル)があり、昔から根強い人気の観光スポットとなっている。そこに建つログハウスでボリューム満点の「そば定食」を出す飲食店がすごい。店の名前は「最高地点」。満月よりもその前の14番目の月が良いという歌もあるが、「ココがサイコー。最高地点に行ってきたよ!」というのは結構な土産話になるそうだ。
蔵王でゲートの前で雪だるまを作ったよ、というのは良い話のようにわたしには思えるし、なにほどか共感もしたのである。この蔵王物件の話は12月25日に放送される予定です。(宮城・岩手・秋田担当 中村健二)
 ▲バイクで来ていたカップルは可愛いサイズの雪だるまをこしらえてくれた。
▲バイクで来ていたカップルは可愛いサイズの雪だるまをこしらえてくれた。
(文化放送「大人ファンクラブ」毎週土曜日06: 25 より。中村の放送回は毎月第4週目)












 ▲赤茶けた排水溝からは湯煙が立ち昇っている。
▲赤茶けた排水溝からは湯煙が立ち昇っている。 ▲田園の先にある蔵王連山は黒い雲に覆われていた。
▲田園の先にある蔵王連山は黒い雲に覆われていた。 ▲エコーライン入り口の大鳥居。
▲エコーライン入り口の大鳥居。
 ▲バイクで来ていたカップルは可愛いサイズの雪だるまをこしらえてくれた。
▲バイクで来ていたカップルは可愛いサイズの雪だるまをこしらえてくれた。
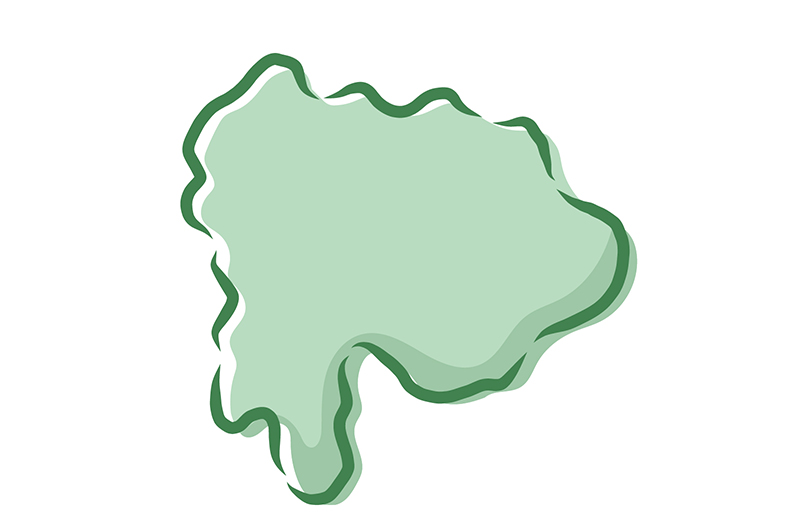



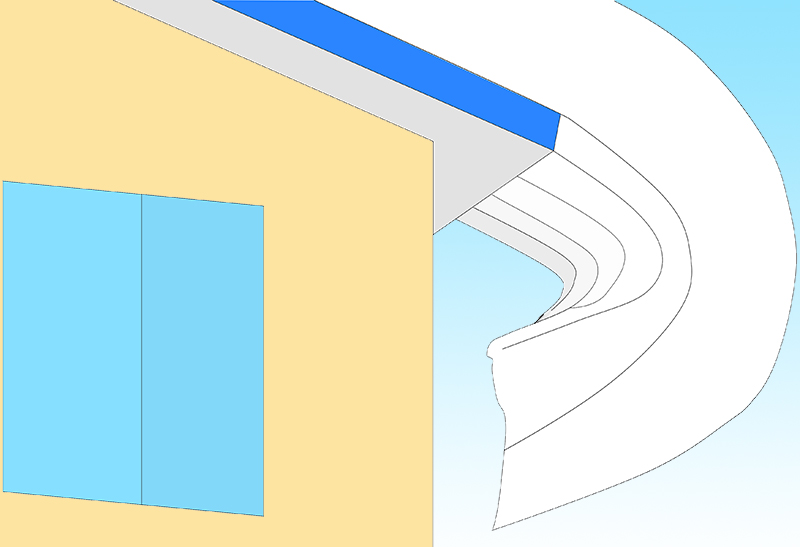

 ▲金谷の市街地を望む高台。その先、大井川がゆったりと流れ、今では橋が何本も架かっている。
▲金谷の市街地を望む高台。その先、大井川がゆったりと流れ、今では橋が何本も架かっている。 ▲東海道金谷宿の石畳。
▲東海道金谷宿の石畳。
 ▲富士山静岡空港は広大な丘陵地帯にあるが人影もまばら。
▲富士山静岡空港は広大な丘陵地帯にあるが人影もまばら。
 ▲井伊家の菩提寺「龍潭寺(りょうたんじ)」は浜松市北区引佐町にあるが、この写真は滋賀県彦根市の「龍潭寺」。
▲井伊家の菩提寺「龍潭寺(りょうたんじ)」は浜松市北区引佐町にあるが、この写真は滋賀県彦根市の「龍潭寺」。


 ※写真はイメージです。
※写真はイメージです。