 ▲中腹から見る山の頂。
▲中腹から見る山の頂。
岩手県花巻市、遠野市、宮古市の境に雄々しくそびえる山「早池峰山」。みちのく岩手事務所がある遠野市でも、石上山(いしかみやま)、六角牛山(ろっこうしさん)と共に、「遠野三山」として、古くから住民に親しまれています。
岩手山に次ぐ岩手第二の高峰(1917m)であり、日本百名山にも名を連ねているため、毎年県内外から多くの登山者が訪れる名山でもあります。山開きは例年六月の第二日曜日に行われ、その日は年間を通じて最も多くの登山者が集まります。
また、周辺地域に伝承されている早池峰神楽の起源と言われている岳神楽(だけかぐら)が、山頂で荘厳に奉納されます。花の百名山にも選ばれている早池峰山では、初夏になると固有種のハヤチネウスユキソウという美しい白い花が見られます。その姿はエーデルワイスに非常に似ており、ワイン産業が盛んな麓の花巻市大迫町(おおはさままち)では「エーデルワイン」という銘柄のワインが毎年生産されています。
 ▲山頂での神楽奉納(2016年)
▲山頂での神楽奉納(2016年)
登山ルートは山開きが行われる「小田越コース」が一般的で、「河原の坊コース」は現在閉鎖中。山開きから8月まではマイカー乗り入れ規制があり、岳集落の駐車場よりシャトルバスでの入山になります。
コロナウイルス拡大の影響により要確認ですが、是非みなさんも岩手の山の魅力を感じにいらして下さい。(みちのく岩手事務所 佐々木泰文)
 ▲山腹からの景色。
▲山腹からの景色。
岩手県の物件一覧はこちら


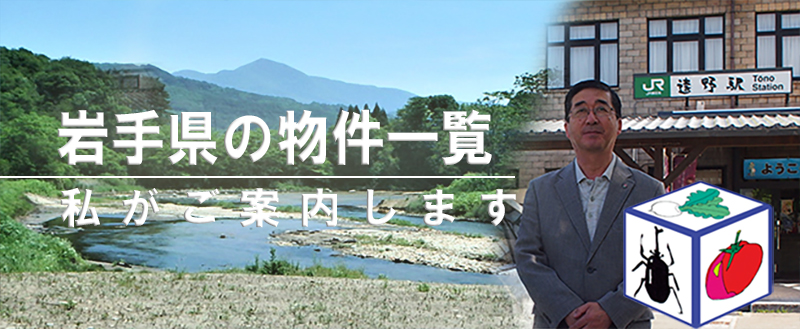


 ▲韮崎駅前にある「球児の像」。
▲韮崎駅前にある「球児の像」。 ▲賢治が東京麹町の栄屋旅館から嘉内に宛てた手紙(「ニコリ」にて)。
▲賢治が東京麹町の栄屋旅館から嘉内に宛てた手紙(「ニコリ」にて)。 ▲移住相談窓口のある駅前ビル。
▲移住相談窓口のある駅前ビル。 ▲韮崎大村美術館入り口にある「ニーラ」の看板。
▲韮崎大村美術館入り口にある「ニーラ」の看板。



 ▲カッコウの写真。
▲カッコウの写真。 ▲北杜市は田植えの時期を迎えました。(北杜市高根町)
▲北杜市は田植えの時期を迎えました。(北杜市高根町)

 ▲静岡市郊外の登呂遺跡。復元された竪穴式住居が立ち並び、古代よりこの地に営みがあったことが知られる。
▲静岡市郊外の登呂遺跡。復元された竪穴式住居が立ち並び、古代よりこの地に営みがあったことが知られる。 ▲静岡の魅力はなんといっても海。甲斐の虎・武田信玄が欲した駿河湾の海岸線。
▲静岡の魅力はなんといっても海。甲斐の虎・武田信玄が欲した駿河湾の海岸線。 ▲用宗海岸。写真には写っていないが堤防には釣り人が多数、沖合でジェットスキーを楽しむ姿もある。
▲用宗海岸。写真には写っていないが堤防には釣り人が多数、沖合でジェットスキーを楽しむ姿もある。 ▲用宗漁港の目の前にある「みなと横丁」はリノベーションして外観・内装とも新しく生まれ変わった。
▲用宗漁港の目の前にある「みなと横丁」はリノベーションして外観・内装とも新しく生まれ変わった。 ▲「おともたび」GPSを利用したアプリは、色々な地域での展開も考えられて楽しみ。
▲「おともたび」GPSを利用したアプリは、色々な地域での展開も考えられて楽しみ。