 ▲モダンな紫波町役場。
▲モダンな紫波町役場。
色の名が付く日本の自治体は数多い。青、赤、白、黒(玄)といったら土俵の房下がりではないが、北海道から九州まで数多く存在している。その中で「紫」の付く自治体は日本に二つしかない。「筑紫野市(ちくしのし・福岡県)」と今回ご紹介する「紫波郡紫波町(しわぐん・しわちょう岩手県)」だ。
この「紫波町」、名前の由来は多々あるという。地名とは、地形と有力者と寺社仏閣がそのルーツだとわたしは考えているので、今回注目した「紫波」の謂れとは、わたし的には次の三つに絞られる。
1)北上川の河岸段丘の縁へりが「ツバ」というらしい、の転意→これは現在ダム工事が行われて社を移転中の「志賀理和気神社」(「しかりわけ」と読む。しがと濁らない)の場所からみてもよくわかる。この名前のなかにも「志」と「和」がある。
2)室町時代にこの地を治めていた足利氏の一派・斯波氏(しばし)が日詰の高水寺城(こうすいじじょう・現在のサクラの名所である城山公園)を拠点としていた。
3)盛岡と結ばれた稲荷街道沿いにある有力な、地元では日本三大稲荷神社の一つと言われる「志和(しわ)稲荷神社」がある。境内には樹齢千二百年の杉の御神木があり、町の天然記念物だ。
 ▲ビューポイントでもある東根山。
▲ビューポイントでもある東根山。
でもなぜ「紫の波」なのだ?
一説にあるように、斯波氏の治めた北上川の川面が陽の照り返しで紫の波のように輝いていた、だから今日から「紫波」にしようという説が安易な割にわたしには面白かったけれども、いかがでしょう。
この紫波町は隣接の紫波郡矢巾町(やはばちょう)と並んでいまや県内でトップクラスの人気を集める自治体となっている。超大型商業施設と岩手医大病院の進出によるらしい。全国的にも県庁所在地に隣接した小さな町が脚光を浴びている例がほかにもある。
それは、当町の中心に位置する紫波町役場やオガールプラザ(図書館と地域交流センター)そしてそこに整然と区画された街並みを見ればすぐによくわかる。町の企画課の担当者の話では「移住者も普通に暮らしています」とのこと。
 ▲町内に四つある酒造メーカーのひとつ「月の輪酒造」。
▲町内に四つある酒造メーカーのひとつ「月の輪酒造」。
要するに特別扱いはせず、何かやりたいことがあれば応援しますというスタンス。事実、町産のりんごを使ったホップサイダー(アルコール分6・5%)を製造販売しているのは、外国語教師として町に赴任経験のあるアメリカ人だ。また、ラ・フランスやリンゴなどのくだもの、野菜、もち米などの農家の産直所はいまや十箇所を数える。
町の面積は二百四十平方キロメートル、人口は三万二千人の活気ある町それが「現在の紫波町」だといえる。北上川が流れ、国道4号線や東北道インターや鉄道駅のある中央部と、伸びやかな田園と奥羽山脈が見渡せる東部地区(今月号掲載の紫波町の住宅(16764N))も、そして町境にあるコタツのような形で親しまれている東根山(あずまねさん・標高928メートル)の麓の西部地区。その西部地区には清流を利用した南部杜氏(なんぶとうじ)発祥の地として名高い酒蔵も点在している。名水の基となる「水分神社」には水を汲みに来られる方々が後をたたない。
 ▲名水を汲みに来る人が後を絶たない水分(みずわけ)神社。
▲名水を汲みに来る人が後を絶たない水分(みずわけ)神社。
この稲荷街道から見下ろす市街地はどこか信州安曇野の山麓線あたりの牧歌的な雰囲気を彷彿とさせる。おいしい「たまご家」もある。東北道紫波インターから3分のところには、純手うちさぬきうどん「たかのはし」がある。ここでの食事代はうどんを食べたあと自己申告して支払うようになっている。平日の昼前にもかかわらず席は半数以上埋まっていた。
またこの紫波町は保育所・幼稚園、小学校が各十一箇所、医療機関が三十二箇所もあり、子育て世代には特に住みやすい環境といえるかもしれない。町の担当者も明るく元気だ。(北東北担当 中村健二)
 ▲たかのはしの手打ちうどん。アットホームな雰囲気も人気を集める。
▲たかのはしの手打ちうどん。アットホームな雰囲気も人気を集める。
=====================================
紫波町企画課総合政策係電話 019-672-6884(直通)メール対応可(※町のHPより)
〒028-3392岩手県紫波郡紫波町中央駅前二丁目3-1


 ▲トオヌップ展望台より。
▲トオヌップ展望台より。 ▲風のない日、田んぼは水鏡に。
▲風のない日、田んぼは水鏡に。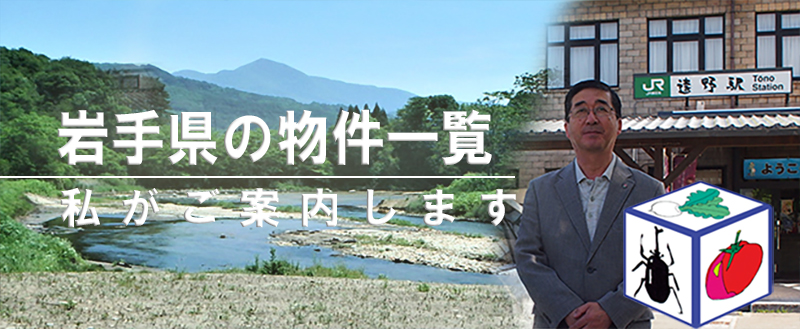



 ▲常連の男の子?は大きな手袋をしてお母さんのお手伝いです。
▲常連の男の子?は大きな手袋をしてお母さんのお手伝いです。
 ▲家族単位の味噌仕込みもご夫婦仲よく手際良く作っていました。
▲家族単位の味噌仕込みもご夫婦仲よく手際良く作っていました。



 ▲田舎膳のお弁当。男の子は私の作る田舎膳のファンらしい。嬉しいです。
▲田舎膳のお弁当。男の子は私の作る田舎膳のファンらしい。嬉しいです。

 ▲「味噌の神様の居場所が違う~ !!」味噌を仕込んで娘の宝物になった木桶です。
▲「味噌の神様の居場所が違う~ !!」味噌を仕込んで娘の宝物になった木桶です。





 ▲道の駅南きよさと。鯉のぼり500匹が大空高く舞い上がる。4月上旬~5月中旬頃。(北杜市高根町)
▲道の駅南きよさと。鯉のぼり500匹が大空高く舞い上がる。4月上旬~5月中旬頃。(北杜市高根町) ▲混み合う峠道(イメージ写真)
▲混み合う峠道(イメージ写真) ▲5月上旬頃に田んぼの水張が始まる。奥に富士山。(北杜市長坂町)
▲5月上旬頃に田んぼの水張が始まる。奥に富士山。(北杜市長坂町) ▲黄昏時に空の色を映す水田。(北杜市高根町)
▲黄昏時に空の色を映す水田。(北杜市高根町) ▲盛岡市の御所湖畔にある「盛岡手づくり村」。
▲盛岡市の御所湖畔にある「盛岡手づくり村」。 ▲場内にはファミリー客の姿も。
▲場内にはファミリー客の姿も。