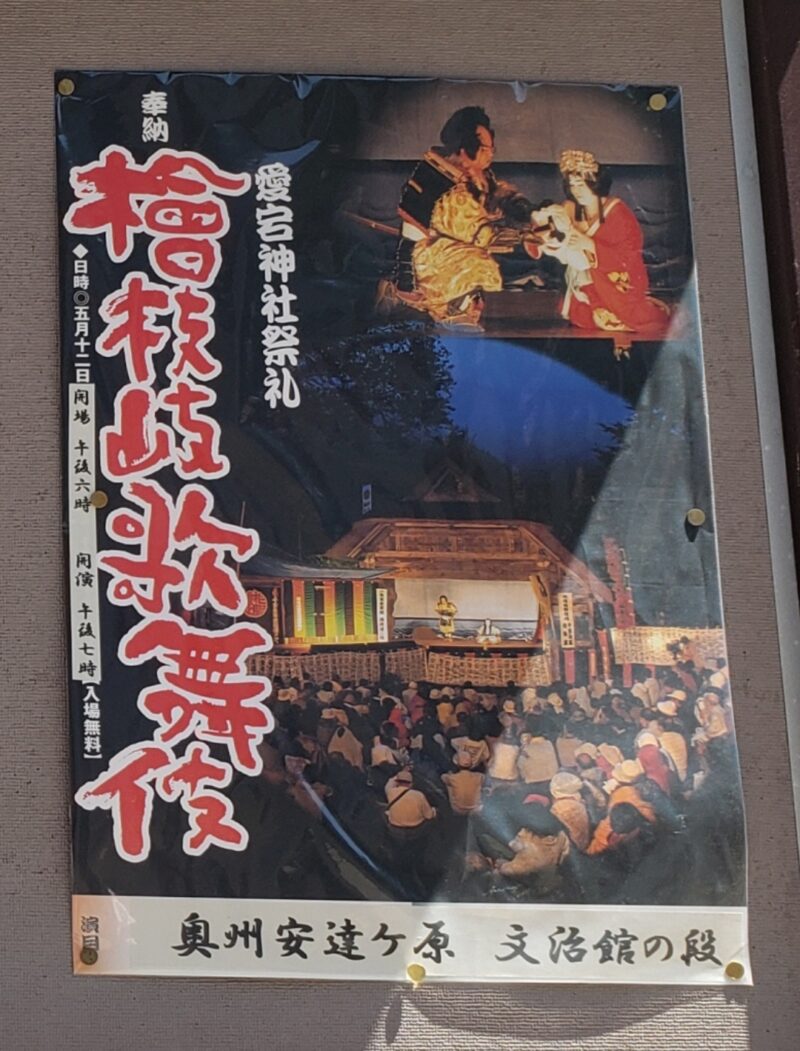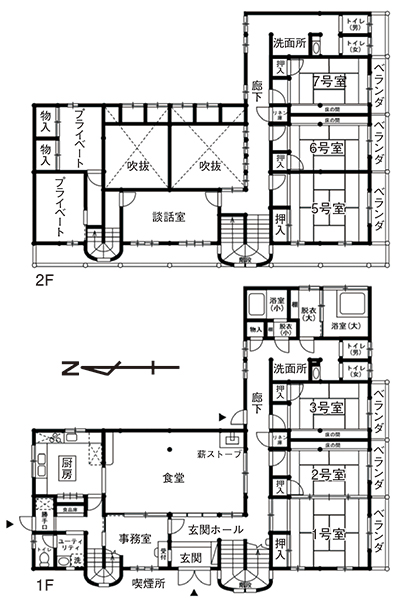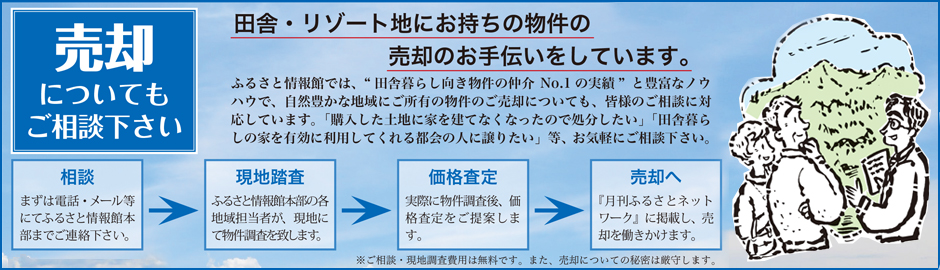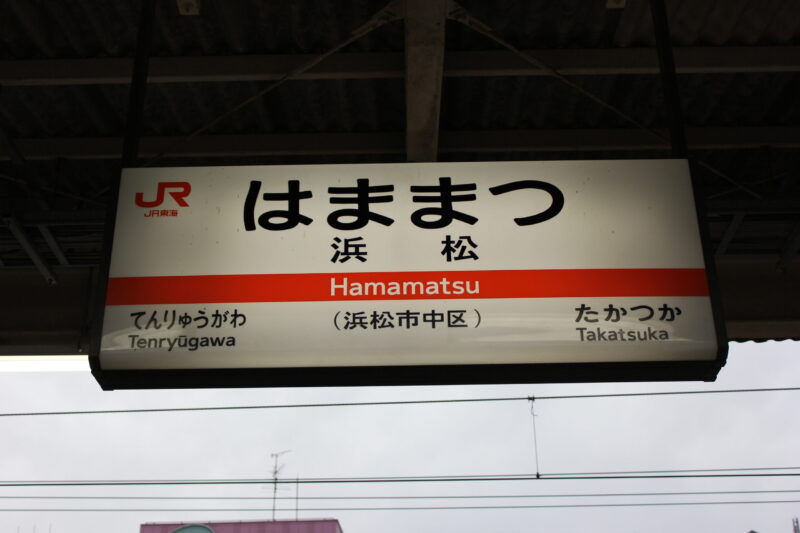▲強い日差しの中、稲が青々と育つ。遠くに空と雲と富士の姿。(山梨県北杜市)
▲強い日差しの中、稲が青々と育つ。遠くに空と雲と富士の姿。(山梨県北杜市)
気象庁の今年の7〜9月にかけての3カ月予報では、全国的に気温が平年よりも高く、昨年に続き「猛暑」となりそうとのこと。
昨年2023年の日本の夏の平均気温は、統計開始以来1位となり、過去最も暑い夏となりました。年々温暖化が進んでいるという事でしょうか。
北杜市の夏といえば、まずはその気候そのものが大変な魅力となります。
一概に北杜市といっても、地形や標高、日照条件などが様々です。
ふるさと情報館の八ヶ岳事務所がある場所は、標高760mと北杜市としては低め、近くに森はなく、日当たりの良い地形です。こういった場所ですと、真夏の日中は気温がぐんぐんと上がり、室内ではエアコンをつけないと過ごせない状況となります。
そんな場所でも、夏の夕暮れとともに気温が一気に下がり、涼しく心地良い風が入ってきます。朝は夜間に冷えた空気の中、一日がスタートできます。
場所を変えて、北杜市で最も涼しい場所はどこでしょうか?
実際に住まわれている方の話を聞くと、まずは標高が高いところ、標高1000mは越えたいところ。さらに森の中だと日中も涼しく過ごせるようです。落葉樹の森の中にある家はとても素敵な環境と言えるでしょう。
冬の間は葉が落ちて、日差しが降り注ぎ、春から夏にかけては緑のカーテンが家を包んでくれる。
樹木は水を吸い上げて生きています。樹木の間を風が通る時に、樹木の中の水が、風を冷やしてくれます。そういった自然のクーラーによる風が、日中も届けられる森の中は、最高の夏の住まいと言えるのではないでしょうか。
「エアコンなんて無いよ」、「付けたいと思ったことも無いよ」、「我が家は扇風機だけは必要かな」と嬉しそうに話す、別荘談義に花が咲く、北杜市の夏の光景です。
最近、北杜市で別荘をご購入されたAさんと雑談した時のこと。
Aさんは、10年位にわたって関東近辺で別荘を探してきました。場所を決めずに別荘探しを始めた方が、数あるエリアの中から最終的に北杜市を選んだ、決め手が気になりお聞きしました。「ここがとっても居心地が良かったから」とシンプルな答えが返ってきました。
 ▲夏は野菜が豊富。直売所をまわるのが楽しい。
▲夏は野菜が豊富。直売所をまわるのが楽しい。
近年は夏の間、貸別荘に半月ほど過ごしたこともあったそうで、その暮らしの中で、過ごしやすい気候に感動し、旬の野菜の美味しさに驚き、その野菜が安価に買えることに喜び、さらにお蕎麦屋さんが沢山あること等、自分にとって居心地が良い場所だと気づいたとのことです。
夏のこの時期、直売所では旬を迎えた夏野菜が並びます。そしてAさんがご購入された別荘は、高原の森の中の涼やかな立地。美味しい野菜を食べ、夜は涼しい環境の中、ぐっすりと眠ることができ、朝の目覚めも良い。夏の過ごし方としては最高ではないでしょうか。
ふと、室町時代の僧侶である一休の、「人生は食うて糞して寝て起きて…」の言葉を思い出しました。
人の一生とは、食べる、排せつ、寝る、起きるだけ。北杜市の夏はこのシンプルな生活を送るには適した環境と言えそうです。(八ヶ岳事務所 大久保武文)