 ▲みずみずしい水田(北杜市大泉町)
▲みずみずしい水田(北杜市大泉町)
梅雨時の山里は新緑の時期になるとよりいっそう緑が濃くなってきます。みずみずしい水田は周囲の山々を映し出し、ひと雨ごとに苗は成長していきます。関東甲信地方の梅雨入りは平年で6月8日(昨年は6日でした)。夏本番前の慈雨の季節が約ひと月ほど続きます。
北杜市の市域は602平方キロメートルで、山梨県の中では一番大きな市となっており、そのうち約5000ヘクタール(市面積の8.4%)がいわゆる農地となっています。市内・武川町(むかわまち)は米どころとしても知られており、「農林48号」は幻のコメとも言われるほど。花崗岩質の土壌がコメ作りに合っているとも。また、ある団体の職員から聞いたところによると、中央道長坂インターを出たところの高根町五町田あたりがうまいコメの生産地になっているとか。
真偽のほどは確かではありませんが、私はその辺りの農家から毎年直接コメを買っています。北杜市は県内きってのコメどころで、その生産現場の端緒となっているのがこの時期の雨の降り具合と密接に関わっていることだけは確かです。
昨年は北杜市大泉町では6月20日に1日で30 ㎜以上の雨を観測しています。この時期の物件見学は雨具の用意とともに防寒対策も忘れずに。土地の水はけ状況のチェックも念入りに行うこともお勧めします。
 ▲田植えの風景(北杜市長坂町)
▲田植えの風景(北杜市長坂町)
◆北杜市市内の空き家の特徴 その3 移住者の住まい
私がふるさと情報館に入社したのが1995年3月、そして八ヶ岳のふもとの小淵沢町に家族とともに移住したのがその2年後の1997年8月のこと(長野オリンピックの前年)。すでに22年ほどの歳月が流れたことになります。不動産の売買においてもすでに1000組以上の方々をこの八ヶ岳で仲介させていただくことができました。
その中には20世紀の終わりに60歳前後で現在の北杜市へ移住された方も多くいらっしゃいます。考えてみたらそうした方々の八ヶ岳暮らしもすでに20年を超えています。御歳80歳をすでに過ぎた方も。その中には都会にいるお子さんに「お母さん、もうそろそろ大泉の山の中からウチ(都市部にあるもとの家)に戻ってきて!」と切実な訴えをされたり、「夫婦とも足腰丈夫なうちに温暖な鎌倉に帰ります」とお話をされたこともあります。もちろん八ヶ岳を「終の棲家」と捉える多くの方々もいらっしゃいますが・・・。
 ▲移住者宅の物件化例(北杜市長坂町)
▲移住者宅の物件化例(北杜市長坂町)
4月27日付『山梨日日新聞』によると、山梨県の空き家の数は約9万戸、総住宅数(42.3万戸)に対する空き家率は21・3% と前年よりも減少したにもかかわらず、いまだ全国1位のままです。北杜市においては、【別荘】という空き家、【実家】という空き家のほかに、【移住者の住まい】が空き家になることがますます増えていく可能性が高くなってきます。 しかしながら、いま八ヶ岳南麓の不動産が活況を呈しているのは、新築住宅の需要増ではなく、移住者宅の再売りのケースなのです。
20世紀後半のかつての移住者の良質な住宅(愛着を持って大事に住まわれてきた)が、令和の時代の移住者にとって値ごろ感ある物件(移住というキーワードで結ばれた)になりつつあります。(八ヶ岳事務所 中村 健二)
 ▲八ヶ岳事務所も花につつまれています。
▲八ヶ岳事務所も花につつまれています。
==================================================
★☆★遠方からの物件見学の際は、「田園暮らし体験館」がお得です!
◆空き家大募集中! 八ヶ岳岳事務所には「一般社団法人空き家相談士協会」認定の空き家相談士が常駐しています。相続手続きや農地や山林、築100年以上の母屋の有効活用など空き家に関する相談を承っております。(要予約、相談無料。担当は中村)
小淵沢物件一覧






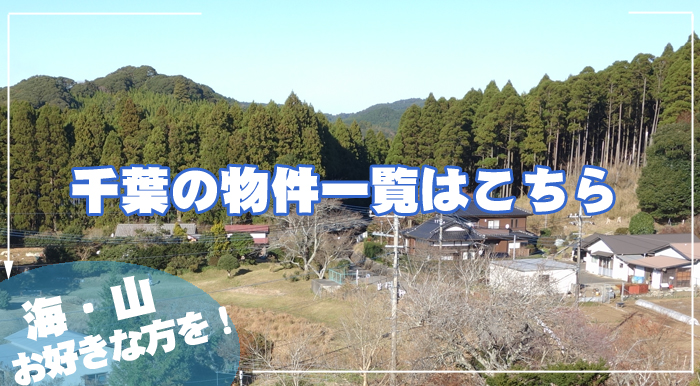




 歳月人を待たず。田舎に暮らし始めたらすぐやっておかないと、後年ホゾを噛むことのひとつに
歳月人を待たず。田舎に暮らし始めたらすぐやっておかないと、後年ホゾを噛むことのひとつに