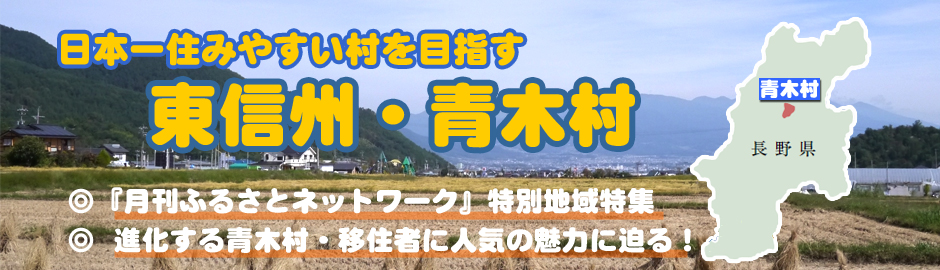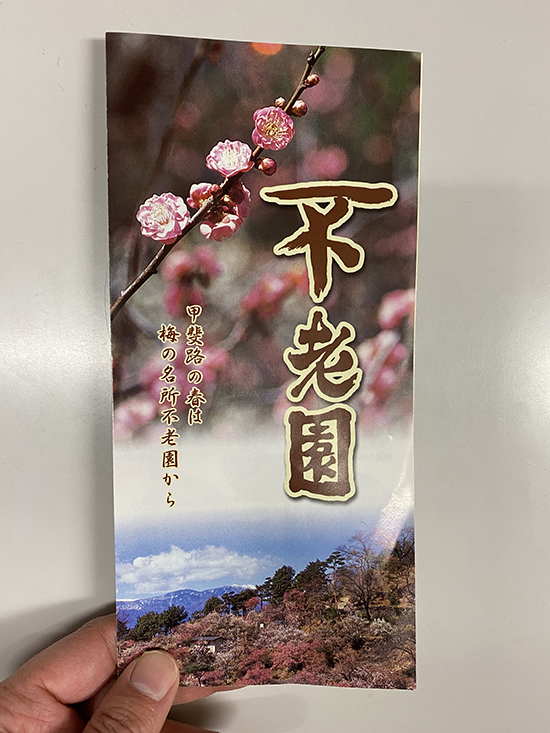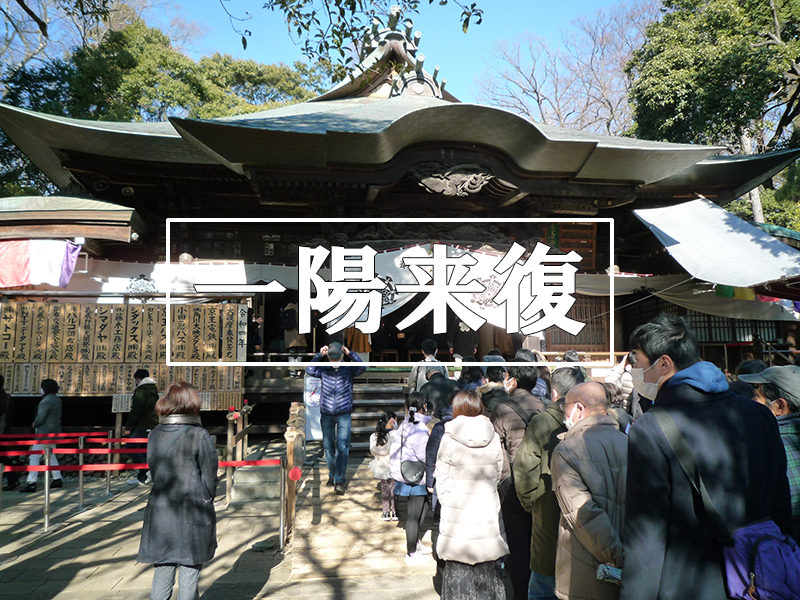▲田野畑村(たのはたむら)の景勝地・北山崎(きたやまざき)。沿岸北部の海岸段丘を一望できる。
▲田野畑村(たのはたむら)の景勝地・北山崎(きたやまざき)。沿岸北部の海岸段丘を一望できる。
昨年2021年12月18日、ついにこの時が来ました。三陸沿岸道路の全線開通です。岩手県の久慈IC~譜代IC間の開通により、青森県八戸市から宮城県仙台市までの太平洋沿岸部を1本で貫く、総延長359㎞の三陸沿岸道路が完成したのです。
みちのく岩手事務所がある遠野市からも沿岸部への移動が大変便利になり、自身がこれまで岩手県内で一番移動に時間がかかると感じていた『あまちゃん』の舞台、沿岸北部の久慈市にも2時間半ほど、南も宮城県の気仙沼や石巻はもちろん、東北一の都市である仙台へも内陸の東北自動車道を利用するルートに代わる選択肢ができました。
 ※東北の自動車道地図(国交省管轄ページより)
※東北の自動車道地図(国交省管轄ページより)
岩手県の面積は15280㎡と北海道に次いで2番目の大きさ。車で岩手を訪れた、または通過した事がある方であればその広さや長さを体感した事があるでしょう。さらに沿岸部は隆起海岸が発達した北部にリアス式海岸で知られる南部と海岸線が非常に入り組んでおり、太平洋に面する海岸線をピーンと伸ばした距離は700㎞を超えるとの事。東京から直線距離で北は盛岡、西は広島まで到達する長さになります。
これまで沿岸部の主要道路だった国道45号線も、その地形に倣って曲がり道が多く、高低差もあるため海岸なのに峠越えのような道のりでした。一方、新たにできたその三陸沿岸道路は、大部分が海を見下ろす高い場所に架けられており、時間距離の面でも心の面でもだいぶゆとりをもって運転する事ができます。ただ、積雪はあまりない地域ではありますが天候による路面状況への注意が必要なのと、海からの強い横風に煽られる事もあるので安全運転を心がけましょう。
 ▲宮古市(みやこし)の浄土ヶ浜(じょうどがはま)。さっぱ船遊覧ではカモメやウミネコが同乗してくる事も。
▲宮古市(みやこし)の浄土ヶ浜(じょうどがはま)。さっぱ船遊覧ではカモメやウミネコが同乗してくる事も。
 ▲釜石市の釜石大観音。釜石中央インターチェンジ。
▲釜石市の釜石大観音。釜石中央インターチェンジ。
私自身も昨年の暮れから2回ほど石巻市の物件調査で三陸沿岸道路を利用させていただきました。石巻市へは以前からも何度か足を運んでいるのですが、新しい道路ができるたびにその変化に驚かされます。市街地へは今では遠野市の自宅から140㎞足らず、三陸沿岸道の無料区間を使い2時間ちょっとで行く事ができます。
石巻には市街地を見渡す事ができるイチオシスポット、「日和山公園(ひよりやまこうえん)」があります。また、高台にあるこの公園からは、岩手県中心部を流れる北上川の河口が見下ろせ、その中州には仮面ライダーやサイボーグ007で知られる漫画家・石ノ森章太郎の石ノ森漫画館があるのも見てとる事ができます。
 ▲日和山公園。頂上には神社があり、海や市街地を見渡せる。
▲日和山公園。頂上には神社があり、海や市街地を見渡せる。
岩手県沿岸部には、八戸や仙台から三陸海岸道路を利用できるようになった他、盛岡と宮古、花巻と釜石をそれぞれつなぐ道路も全線開通したため、内陸を通る東北自動車道からのアクセスも非常に便利になりました。また、現段階ではそのほとんどが無料区間となっておりますので、岩手にお越しの際は是非ご利用ください。まだまだカーナビに出ない道路も多いですし、サービスエリアやトイレ、ガソリンスタンドもありませんので、事前に確認等をされることをお勧めします。
みちのく岩手事務所では今後もっと沿岸部の新規物件調査、案内を拡充させていけたらと考えております。どうぞよろしくお願いします。(みちのく岩手事務所 佐々木敬文)
 ▲北上川の河口。中央の白い変わった形の建物が石ノ森漫画館。
▲北上川の河口。中央の白い変わった形の建物が石ノ森漫画館。






 ▲前日もち米を網に入れ、そのまま洗って水に浸し、当日水を切りセイロに入れて蒸します。
▲前日もち米を網に入れ、そのまま洗って水に浸し、当日水を切りセイロに入れて蒸します。


 ▲今年初参加の女性が締めの餅つきの跡継ぎに。頼もし~い!です。
▲今年初参加の女性が締めの餅つきの跡継ぎに。頼もし~い!です。
 ▲何でもできるイッちゃんが先生になって後継者育成中です。
▲何でもできるイッちゃんが先生になって後継者育成中です。 ▲時間がたち固くなった豆もちは切るのが大変ですが、この「もち切り」は便利で楽に切れます。
▲時間がたち固くなった豆もちは切るのが大変ですが、この「もち切り」は便利で楽に切れます。