最新号、3月号の目次を更新しました。
特集記事では最近話題の「住宅のリノベーション」を取り上げています。
リフォームとリノベーションの違いは?その実践例は?
新着物件情報も充実の1冊、ぜひご覧ください。
写真は山梨県北杜市小淵沢町の田舎暮らし実践者からいただいた
「地域での活動と交流・和太鼓」です。

最新号、3月号の目次を更新しました。
特集記事では最近話題の「住宅のリノベーション」を取り上げています。
リフォームとリノベーションの違いは?その実践例は?
新着物件情報も充実の1冊、ぜひご覧ください。
写真は山梨県北杜市小淵沢町の田舎暮らし実践者からいただいた
「地域での活動と交流・和太鼓」です。

最新号、2月号の目次を更新しました。
特集記事では千葉県の北東部、九十九里エリアの紹介をしています。
菜園で作った野菜と、地元産の新鮮な魚が食卓に上るのもこの地域ならでは。
新着物件情報も充実の1冊、ぜひご覧ください。
写真は富士見・原村案内人の方からいただいた「どんど焼き」です。

最新号、1月号の目次を更新しました。
カラーページではではふるさと情報館スタッフが「新春座談会」をおこないました。
2014年の田舎暮らしの動向や2015年の展望について各担当者が語っています。
新着物件情報も充実の1冊、ぜひご覧ください。
最新号、12月号の目次を更新しました。
今回の特集エリアは山梨県の甲州市と山梨市です。
首都圏から近くて景観がよく、温泉があってフルーツがおいしい、
いいとこづくしの地域の魅力をお届けします。
もちろん、新着物件情報も充実の1冊です。

最新号、10月号の目次を更新しました。
今回の特集エリアは那須町です。
御用邸や別荘地のイメージがあるかもしれませんが、
那須の里山は田舎暮らしに人気のスポットなんです。
田園風景と雑木林の景観が特徴の那須の魅力をお届けします。
もちろん、新着物件情報ももりだくさんですよ。
山形〜宮城を訪れた先日の取材、帰路で以前取材させていただいた
Nさんのラーメン屋さんに寄ってきました。
Nさんはもともと宮城県の七ヶ浜町でペンションを経営していましたが、
東日本大震災の津波でペンションは焼失してしまいました。
避難生活を送る中で、「みやぎ蔵王別荘協議会」による
別荘地の物件を被災者に貸与するという取組みを知り、蔵王へ。
借りた別荘で暮らしながらアルバイトで新生活の模索をし、
蔵王町内にある元倉庫を購入して改築。
震災の翌年2012年9月に晴れて「麺王みらい」がオープンしました。
(ここまでが前置きです)

最初に取材でお伺いした時はまだ改築中だった内装もすっかり完成し、
白を基調とした清潔感あふれる店内。
出てきたラーメン(中華そば)は玉子と2枚のチャーシュー、
たっぷりのネギ、ナルト、メンマがのってなんと600円。
スープは煮干しを軸に、あっさりしつつも深い味わい。
実に、本当においしいラーメンを久しぶりに食べました。

首都圏でもちらほらと夏日が出始めた今日この頃。
涼を求めて蔵王へ、そして絶品ラーメンはいかがですか?
(ちなみに蔵王エコーラインは5月末の段階でまだ雪の壁がありました)
もう2週間前のことになりますが、『月刊ふるさとネットワーク』6月号
特集記事の取材で新潟県の中越エリアへ行ってきました。
新潟といえば米どころ、青い田んぼの向こうに越後の山々が…
といけば良かったのですが、取材の時期はまだ僅かに雪が残っている状況。
当然田植えもまだ先で、少し早い田んぼで代掻きをしているくらいでした。
嬉しい誤算だったのは、場所によって満開の桜が見られたこと。
地域や標高によっても開花状況にばらつきはありましたが、
何カ所かで今年2度目のお花見をすることができました。

さすがに6月号で桜の写真は季節が合わないので使えませんが、
ブログでちょっとお裾分けします。

6月号の特集「新潟県・中越エリア」もお楽しみに〜

=======================================
★田舎暮らしの情報満載! 物件情報をいち早くお届け!
★年間購読会員制 『月刊ふるさとネットワーク』 (3600円/年間・送料込)
※まずは1冊無料見本誌をご覧ください!担当者コラム・移住者の体験記等読み物充実!
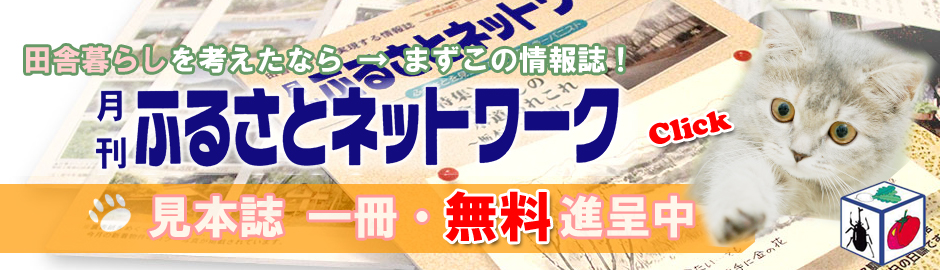
※新着物件情報のパスワードは、本誌物件コーナーの一番始めのページに毎月掲載中!

月刊ふるさとネットワークの「ふるさと発」コーナーで毎月コラムをご執筆いただいている蔵王町・渡辺さんが経営する「ペンションそらまめ」がテレビ番組に登場します。
番組はBS-TBS「伊達な旅紀行〜いいトコ!みやぎ」で、宮城県の観光地や食材・物産などの魅力を紹介する番組です。「旅人の目線で宮城の各地を訪れ、美しい映像や人々の笑顔に出会っていくことで、まるで実際に宮城県を訪れているかのような気分に!」なれるとのこと。
「ペンションでゆっくり蔵王を楽しむ」というタイトルの当日の放送内容は「緑鮮やかな夏の蔵王連峰。市街地から少し離れて、涼しい高原で、森林浴やバードウォッチングなど大自然を楽しむことができる。また蔵王酪農センターでは、乳製品作り、ソーセージ作りなどを体験することができる。夏の蔵王のもう一つの楽しみは、ペンション。森の中には個性豊かなペンションがあり、朝食に美味しい手作りパンなどをゆっくり味わうこともでる。喧騒を離れて、蔵王で爽やかな夏のひとときを過ごしてみませんか。」というもの。
放送日は8月13日(火)の20:54から。是非ご覧ください!
=============================================
☆渡辺さんが経営する宮城蔵王・遠刈田温泉郷ペンションそらまめのホームページ
http://www.soramame-p.com/
「ペンションそらまめ」で検索できます。