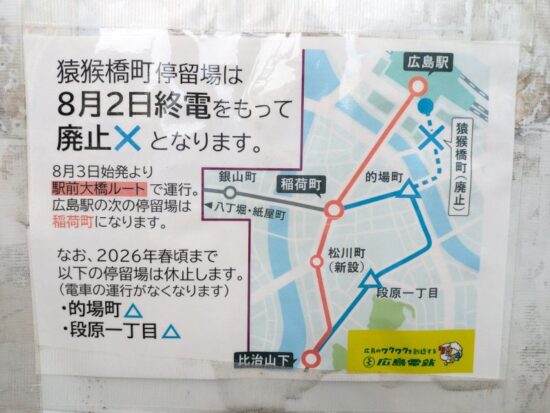▲鳥居の前に広がる瀬戸内海と讃岐平野は一見の価値あり。
▲鳥居の前に広がる瀬戸内海と讃岐平野は一見の価値あり。
旅行を趣味?とする小生。それが齢50を過ぎ、体力の衰えを感じるようになり、いつしか旅行=パワースポット巡りに目覚めました。
パワースポットと言えば神社仏閣、神社仏閣と言えば空海和尚の香川県!(そこは独断的思考ですので何卒ご寛大を)
そこで今回訪ねたのは観音寺市にある高屋神社。当にタイトル通りの鳥居です(これ以外のタイトルは考えても思いつかず)。
神社は本来、神様がいらっしゃるお社(本殿など)に参拝するものですが、ここに至っては主人公が「鳥居?」、いや、正確には「鳥居の前に広がる景色」と言っても過言ではありません(もちろん奥には立派な本宮が鎮座しています)。
標高400mあまりの里山からの眺めはそう珍しいものではありませんが、その眺めが鳥居を介してとなると人間の脳がその価値を何倍にもしてしまうのでしょうか。
ご利益は稲の豊作を司る神様とのこと。今のコメ不足も何とかしてほしいものです。
普段は無人で、御朱印は自動販売機で購入、水洗トイレ完備。頂上近くまでは車で行けます。
時間と体力がある方はミニ登山の参道を一時間くらいかけ、よっこらしょ、どっこいしょと登っていけば、登頂した時の感動は更に大きくなることでしょう。(本部・香川県担当 金澤和宏)
================================
高屋神社~天空の鳥居~(観音寺市役所 商工観光課観光係ホームページより引用)
・下宮までのアクセス
車:高松自動車道大野原ICから車で18分(約8km)、さぬき豊中ICから車で20分(約8km)
境内に駐車場あり
鉄道:JR観音寺駅からタクシーで13分(約4km)
乗り合いバス:1日4便。高屋神社下宮行きのバスはありません。最寄りのバス停から徒歩約10分(約1Km)。
・本宮までのアクセス
徒歩:下宮から本宮まで徒歩約50分。(山道のため、歩きやすい靴でお越しください。)
・天空の鳥居行きシャトルバス
土・日曜日・祝日は、山頂行きシャトルバスを運行しています。