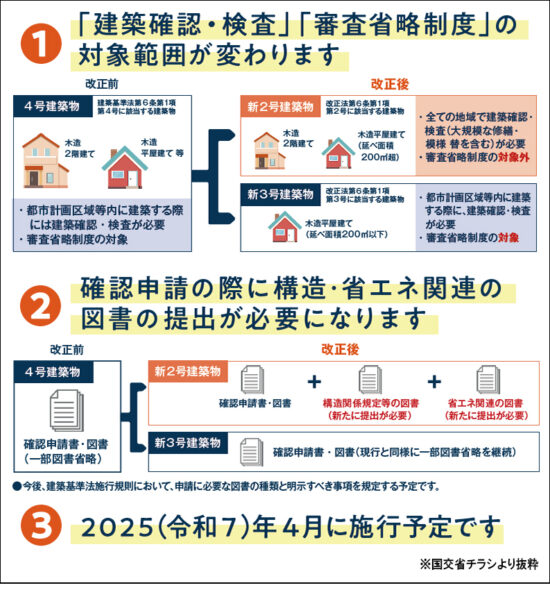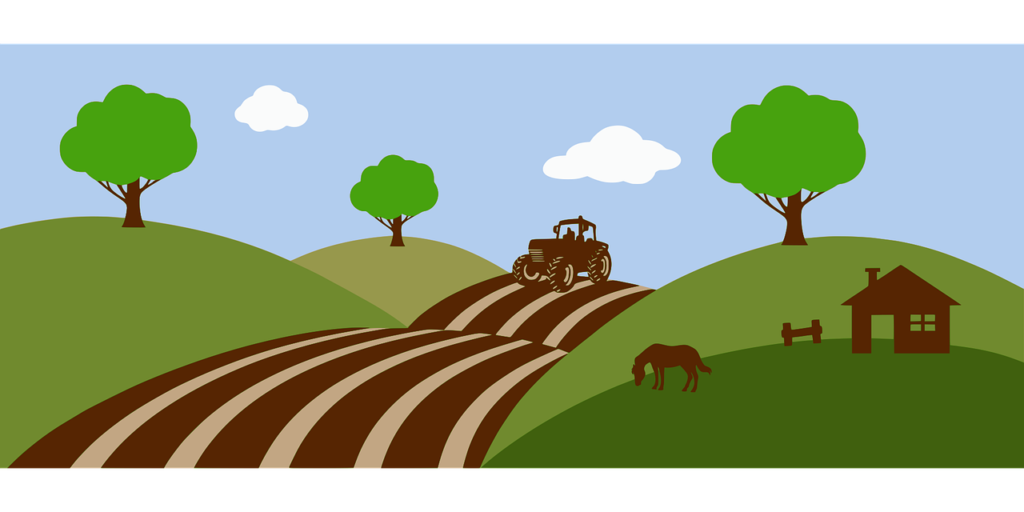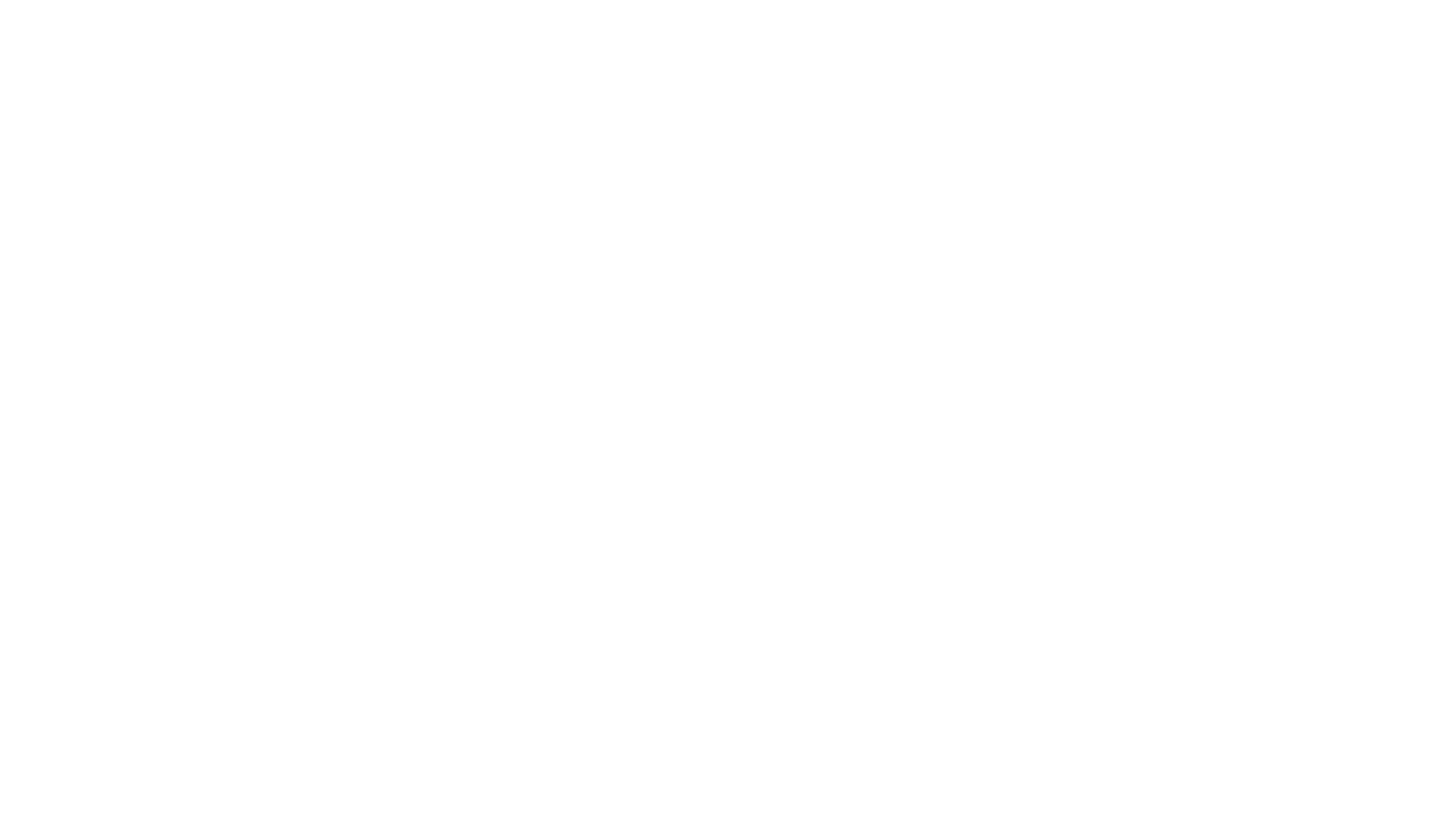▲見たことはあるけど、何の看板かよく知らない。それだけでもイメージ戦略としては成功していると思いませんか?
▲見たことはあるけど、何の看板かよく知らない。それだけでもイメージ戦略としては成功していると思いませんか?
突然ですが、田舎といえばまず連想されるものは何でしょう。
美味しい空気、緑の多い豊かな自然、虫の声や川のせせらぎ等、視覚・聴覚・嗅覚の面から人は過去の記憶に遡って、これと言えばThe・田舎といった要素があると思います。
日本人の心の中には、人生で一度も田舎で暮らしたことがない人でも、これこそ田舎といった光景を瞬時に想像出来るのは、日本人の脳内に標準装備された一種の才能だと考えています。
さてそんな中である一定の年齢層の人には、人生どこかで見た記憶はあるものの、固有名詞や具体的な内容が思い出せない、所謂深層心理にある田舎アイテムがあると思います。
それはズバリ、今回取り上げる「マルフク」の赤い看板もその中の1つではないでしょうか。
株式会社マルフクとは、2002年まで電話加入権を担保に少額融資を行っていた貸金業者で、まだインターネットが普及する以前の1980年代全盛期には、日本全国至る所の田舎にこの赤い広告が約50万枚は存在したとか。
広告ということは自販機と同じで年間いくらかの収入が得られるはずですが、現在この会社自体が貸金業を廃業しているため、少なくとも20年以上は広告主を失い全国で放置され続け今に至るわけです。
 ▲福島県“ 昭和” 村の旧喰くい丸まる小学校。この手の“ 昭和” 木造校舎は、全く自分の世代ではないため親しみはないですが、何故か懐かしさだけは感じることが出来ます。これって前世の記憶なのでしょうか?
▲福島県“ 昭和” 村の旧喰くい丸まる小学校。この手の“ 昭和” 木造校舎は、全く自分の世代ではないため親しみはないですが、何故か懐かしさだけは感じることが出来ます。これって前世の記憶なのでしょうか?
これだけ携帯電話が普及している現代においては、電話加入権なるものがほぼ無価値に思えるものの、昭和中期にはテレビやラジオが貴重な娯楽の一つだったのと同様に、固定電話や葉書も当時としては数少ない通信手段の一つ。
日本の敗戦後、焼け野原となった全国各地において、逼迫する住宅需要に対して供給量が全く追いついていなかった事情から、1990年のバブル景気終盤をピークとして多くの家屋が建築されました(その結果として戦後スギの植林が開始されたものの、円高による安価な外国産木材の輸入や、建築資材の変化等により全国各地で手入れされていないスギが大量に放置され、日本人の4人に1人は患者とされる昨今のスギ花粉問題に繋がってきています)。
しかし2024年現在では、全国に世帯主を失った空き家が約900万戸あるとされ、不動産の担保価値も電話加入権と同様にその位置付けが大きく変わってきたように感じます。
例えば東京のJR中央線最寄り駅から徒歩圏内の新築戸建住宅の最低価格が1億数千万円〜と、絶賛失われた30年真っ只中で可処分所得が一向に上がらない中、夫婦共働き・ペアローン・フラット50という三拍子がもはや当たり前になっている東京の新築事情とは打って変わり、地方の空き家はもはやタダでもいいから手放したいという、上記の実情と比較して信じられないような声が実際にいくつも寄せられており、つくづくモノの価値とは需要と供給の絶妙なバランスから成り立っているものと痛感させられます。
だからこそ、田舎で色褪せた赤いマルフクの看板を見かけると、「夏草や兵どもが夢の跡」と言わんばかりに、時代の移り変わりに翻弄され、空き家で寂しそうに世帯主・広告主を待つマルフクの看板に想いを馳せてしまうのです(本部 髙橋瑞希)
 ▲国土の約4分の1に人口の約95%が住む日本。私たちが取り扱う物件は・・・?
▲国土の約4分の1に人口の約95%が住む日本。私たちが取り扱う物件は・・・?