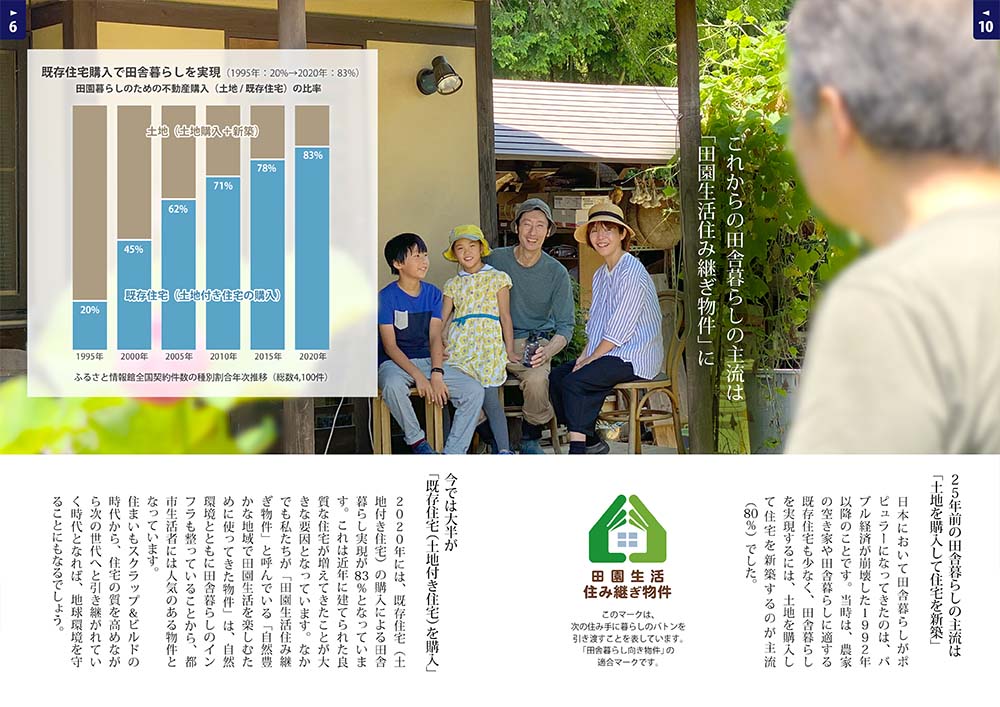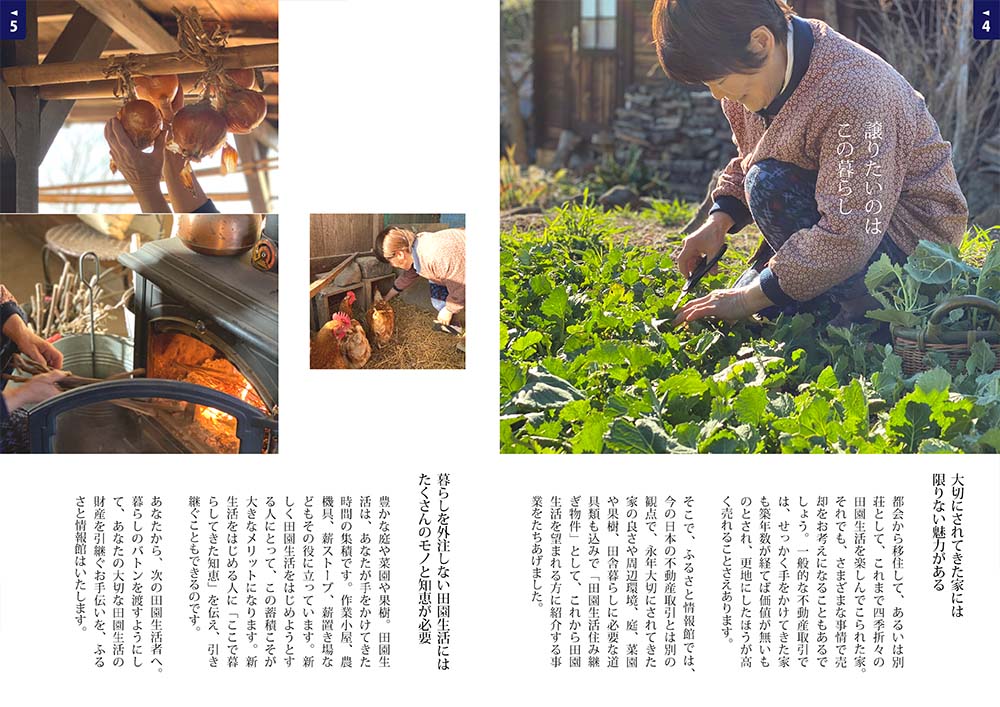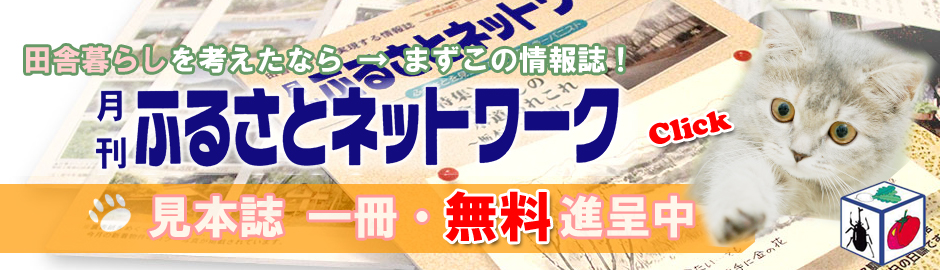山梨県は昔、「甲斐の国」と呼ばれていました。由来は周囲を山に囲まれたいわゆる山峡(やまかい)の「峡」の意に由来するといわれております。名前の通り、四方を山に囲まれているいわゆる盆地地形となり、少ない平坦を有効に活用する為に、先人たちは工夫を凝らしていました。
その一つとして、石垣を用いて傾斜地に平らな面積を増やす方法でした。昔はセメントもコンクリートも有りませんので、石積み技術が重要で、大きさもバラバラな石を積み上げる技術は素晴らしい物でした。
 VやWとなる良い積み方。
VやWとなる良い積み方。
一般住宅や畑、田んぼにも多く用いられています。甲州市塩山にある川村造園(甲州市塩山福生里485 -4)さんには、普段から案内をお願いし、庭木や石垣の事を教えて頂いており、「この石垣は上手に積み上げられている」という物件もありました。どの様な積み方が上手か尋ねると、「『Vの字』に積むのが上手な積み方で、上に乗せた石と下の石の継ぎ目がYになると荷重が下へと伝わり、石が噛み合って強い。『品の』字平に重ねると、作業は簡単で速いけど、噛み合わないからね。横からの加重(土厚)が掛かると押し出されてしまう」との事でした。
信玄公の言葉で「人は城、人は石垣・・・」適材適所で才能を十分に発揮できる場所が重要との教訓ですが、石をどこに配置するかを見分ける技術で長持ちするかが決まると教えて頂きました。(本部 長内 望)
=======================
売却物件を求めています
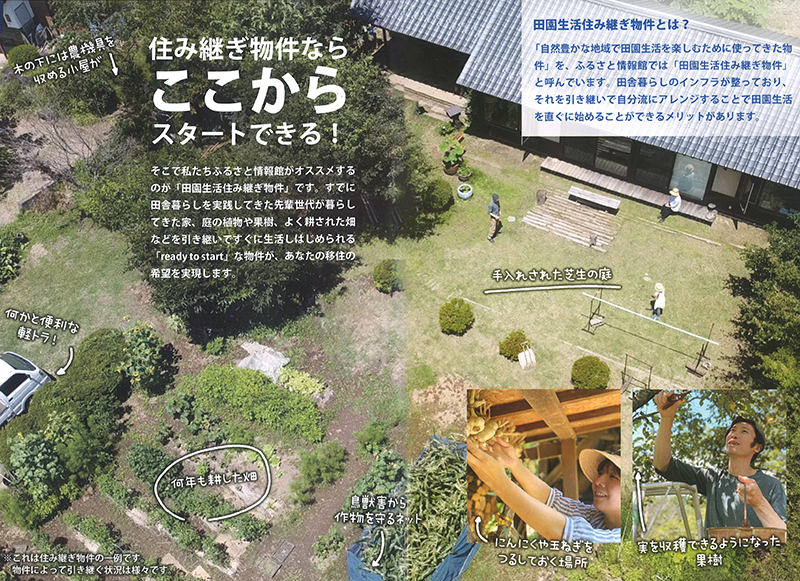
=======================