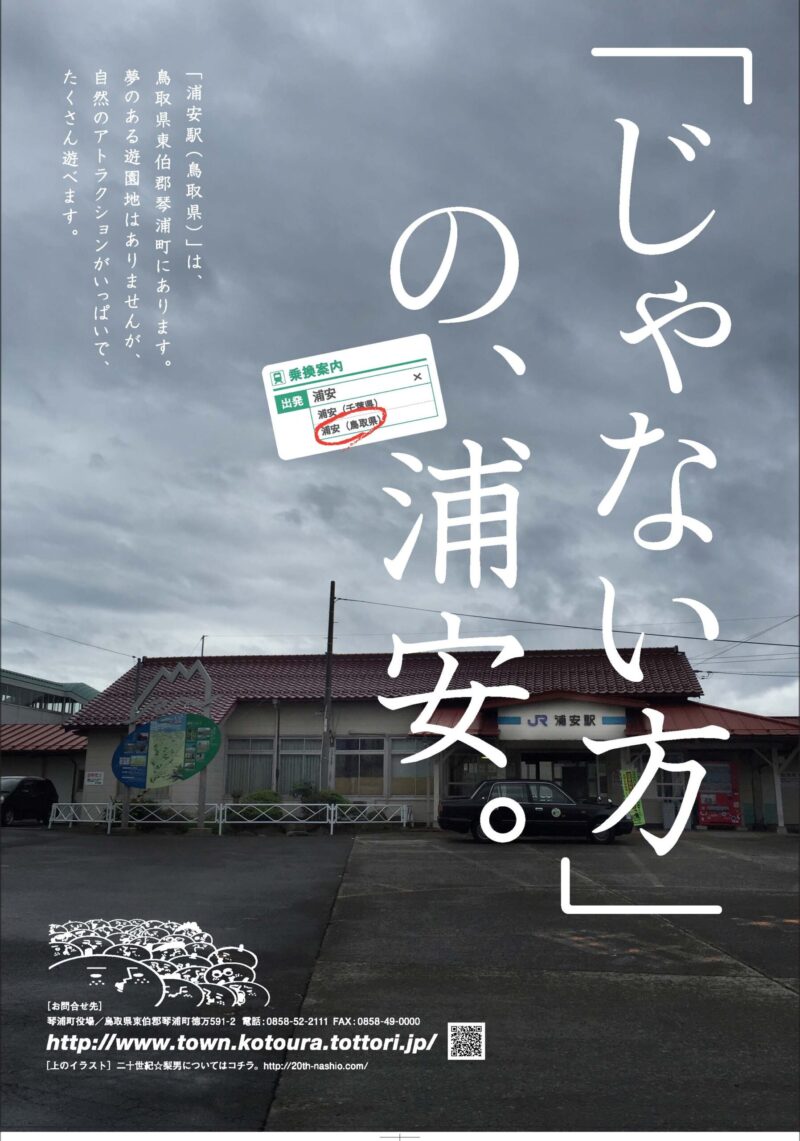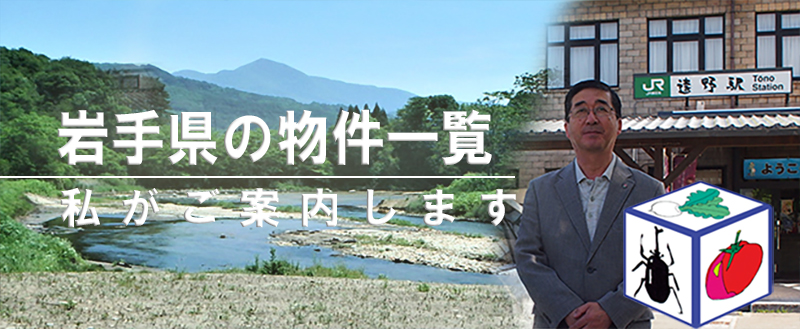▲電車の旅では駅弁も楽しみの一つですね
飛行機や新幹線・高速道路が発達する以前の高度経済成長期の日本は、まだ陸上交通の主役は国鉄の在来線であり、特急列車が文字通り「特別」な急行だった頃、庶民の移動手段は鈍行か急行のどちらかでした。
当時は現代のようにコンビニやスーパーもなく、旅人たちの胃袋を満たしてきたのはいつも大きな籠をぶら下げホームを歩いている駅弁屋さん。列車が到着し「駅弁~駅弁~」と声を上げると、列車の窓が次々と開き、金銭と食料の受け渡しが行われていきます。
籠の中には駅弁の他にお菓子やジュース等も入っており、ポリ茶瓶容器の緑茶や夏期の冷凍みかんと聞いて懐かしい方もいらっしゃるのではないでしょうか。今となってはほぼ絶滅したかに思われた駅弁の立ち売りですが、駅弁ではないものの別の商品を毎日立ち売りしている駅が存在します。
※国鉄とは日本国有鉄道の略で、1987年4月1日にJR グループ(旅客6社貨物1社)へ分割民営化される前に存在した三公社五現業のうちの1つであり、北は北海道から南は鹿児島まで私鉄等を除く全ての鉄道路線を管理運営していた国の公共企業体。

▲1日上下12本の普通列車が止まる秘境駅。

▲旧4連続スイッチバック駅のうち、赤岩駅は周辺集落が無人化したため2021年3月に廃止。
ここは山形県米沢市のJR 奥羽本線(山形線)の峠駅。奥羽山脈を越える難所板谷峠の真ん中にある駅で、防雪シェルターで囲まれた駅の外は鬱蒼とした森しかない秘境駅。
かつては蒸気機関車が険しい板谷峠を乗り越えるために、赤岩・板谷・峠・大沢駅は4連続スイッチバック(※)という全国でも極めて珍しい運転区間となっていました。山形新幹線が1992年に開通するにあたりこのスイッチバックは廃止されましたが、その名残はこの特殊な防雪シェルターが物語っています。
この路線は1899年に開通し、明治から令和に至るまで毎日列車が来る度にホームに立ち続ける人がいます。その人こそが現代において絶滅危惧種である駅での立ち売りを行っている「峠の茶屋」の売り子さんなのです。

▲8個入り1,000円で販売。お釣りいらずでありがたいお値段。立ち売りだけではなく店舗でも販売中。
営業から120年以上の長い年月が経ち、現在売り子を務めているご主人は、先代から数えるとなんと5代目になるとのこと。2022年11月現在、日本国内でほぼ毎日立ち売り販売を行っている駅は、ここ山形県米沢市の峠駅と、福岡県北九州市八幡西区の折尾(おりお)駅とわずか2駅のみ。前者は「峠の力餅」という大福を、後者は「折尾のかしわめし」という三色駅弁をどちらも立ち売りにて提供しています。
ただし九州の折尾駅とは違い、奥羽山脈の真っ只中に位置する峠駅は日本有数の豪雪地帯で、冬期は遅延や運休が発生することもしばしば。予め運休が計画されている日は当然立ち売りはお休みとなりますが、列車が走り続ける限り8時~18時台に峠駅を発着する上下6本の列車で、峠の力餅の立ち売り販売を行っています。ただし停車時間は30秒と非常に短いので、購入の際は予め千円札をお持ちになり、列車最後尾のドアまでお越しください。
他の駅も昨今のコロナ禍や路線の休止で次々と立ち売り販売を取り止める中、昔ながらの立ち売りを続ける峠駅ですが、近年その活躍にも陰りが見えてきました。線路を共用している山形新幹線が、この区間を迂回する新板谷トンネルを建設する計画が持ち上がっているのです。

▲時代や環境の変化はあったものの、120年以上続く立ち売り販売はまさに国宝級の伝統文化だ。
まだ着工に至っていないので、完成したとしてもまだ何十年も先の話ではありますが、もし開通すれば峠駅を含む現在の区間はほぼ間違いなく路線廃止となります。参勤交代で賑わった羽州米沢街道がある頃から、店を続けている峠の茶屋さんには、列車が走り続ける限り、雪にも負けず運休にも負けず、立ち売り販売を続けて頂きたいと心から願ってやみません。(本部 高橋瑞希)
※スイッチバック:主に急勾配を緩和するための特殊な運転方式で、 車両性能が向上した現在は不要になりつつある。
★気になった方は、山形県ホームページ内、『峠駅スイッチバック遺構』をチェック!(https://www.pref.yamagata.jp/110001/sangyo/sangyoushinkou/him_top/him_maincat3/him_09.html)
JR 奥羽本線(山形線)峠駅
 ▲道の駅「雫石あねっこ」。
▲道の駅「雫石あねっこ」。 ▲「はしばの湯」のフードコートで天丼タイム。
▲「はしばの湯」のフードコートで天丼タイム。